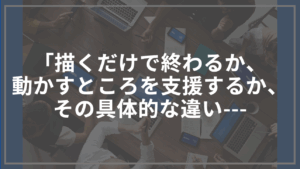費用なのに資産?「原価」と「費用」の違いと利益の見え方の真実
何かモノやサービスを購入したときに対価としてお金を払います。これを一般的には費用といいます。しかし財務会計の世界では、同じ費用に見えても原価と費用という言葉に厳密に分かれます。似ているようで似ていない。この原価と費用について見ていきましょう。尚、財務会計とは、企業の経済活動の結果(損益)や財務状況(資産・負債・純資産)を数値で明らかにし、外部関係者に報告することを指します。
①原価 (棚卸資産原価)
製品、仕掛品、原材料など、販売されたときに売上原価(費用)に転換されるもので、製造原価のことを指します。製品は、必ずしも製造された会計年度に販売されるとは限りません。翌期以降に販売されることもあります。この場合、財務会計上は、製造された製品の原価と売上高を比較せずに、販売された製品の原価と売上高を比較しなければなりません。そこで、製造に要した原価は、棚卸資産(在庫)として資産計上しておき、販売された時に費用とします。製品が販売されたとき、製品(棚卸資産)と引き換えに現金が取得されます。このとき、売れた製品
(棚卸資産)の原価が費用になります。
②費用 (期間費用)
損益計算書に記載される売上原価以外の全て(広告費、人件費、光熱費、賃料、物流費、研究開発費など)の費用のことを指します。これらの費用は、たとえ将来発売する製品の費用、例えば新しい製品のための研究開発費であっても、それは将来の売上ではなく、支出が生じた期間の売上獲得に貢献する支出であると見なされ、支出された期に直ちに費用として計上されます。
原価と費用の違いがわかったところで、利益への影響の違いを比較してみます。
① 原価の利益への影響
=「販売されたタイミング」で費用計上されるため、在庫が増減すると利益がブレます。
製造に要した原価(例:材料費、労務費、製造間接費など)は、まず「棚卸資産(在庫)」として資産計上されます。実際に販売されたときに初めて「売上原価」として費用計上され、利益に影響します。つまり、製品を作っても「売れなければ」費用計上されず、利益は下がりません。一方、製品が売れて在庫が減少すると費用が増えるため、利益が減ります。製品100個を作っても、50個しか売れなければ、残り50個分の原価はまだ費用になりません。この年の利益は相対的に高く見える(在庫の分だけ利益が先送りされる)ことになります。
② 費用の利益への影響
=「発生した期」に必ず費用計上されるため、売上の有無にかかわらず利益を圧迫します。
研究開発費や販促費などの期間費用は、「支出があった期」に全額が費用となります。将来の売上に貢献するであろう支出でも、その期の売上と対応させて利益を計算します。売上が未発生でも費用になるため、利益が下がりやすくなります。今期に1億円の研究開発費を使っても、来期以降にしか売上が立たない場合、今期の利益は大きく減少します。
経営的な視点での見方
棚卸資産原価が占める割合が多いビジネス(製造業など)では、「在庫の増減」で短期的に利益がブレやすいため、在庫評価が肝となります。在庫が増えると見かけ上利益が増えて、在庫が減ると見かけ上利益が減ります。一方、期間費用が占める割合の多いビジネスでは、将来への先行投資が利益を押し下げる傾向にあり、損益計算書が悪化します。しかし短期的な損益計算書の状態をもって業績を判断するのは危険です。今は費用が先行しても、将来に売上が大幅に伸びる可能性もあるからです。
原価と費用は定義が異なるだけでなく、ビジネスモデルの違いによる利益の影響が大きく異なることがわかりました。現在のビジネスがどちらに当てはまるか考えてみるのもよいのではないでしょうか。