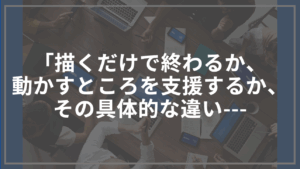「20点の企業に90点の助言は毒になる」──状況別コンサルの鉄則
今回も引き続き弊社の強みを解説していきます。これまで、強みとして課題創造、捨てる戦術、を挙げました。今回は、状況別コンサルティング技法です。これは、企業の企業規模や仕組レベルの状況に応じてコンサルティング技法を変える、という意味です。テーマに応じてコンサル技法が異なるのはよくあることです。例えば、大規模なITシステム導入と投資先判断のビジネスDDではアプローチや時間軸、用いる考え方が全く異なります。しかし、企業規模の大小や仕組のレベルに応じて技法を変える、というのはあまり一般的ではありません。
基本的に、企業の規模とその企業の内部で適用されている仕組/マネジメントレベルは比例するため、同じ塊として捉えます。企業規模が大きいほど仕組レベルは高く、企業規模が小さいほど仕組レベルは低い。規模が大きくて仕組レベル60点の企業Aと、規模が小さくて仕組レベル20点の企業Bでは、どのようにコンサルティング技法が異なるのでしょうか。
ある経営コンサルタントがいて、特定のテーマでコンサルティングを企業に提供するとします。そのコンサルタントは、90点の仕組レベルにできる実力があるとします。この方は、企業Aと企業Bにコンサルティングをする場合、どのような進め方をするのでしょうか。企業Aと企業Bそれぞれに対して同じ考え方で90点を目指すコンサルティングを行います。そうすると、企業Aは元々60点のレベルがあるので、コンサルタントが提示する考え方や粒度が細かい管理手法もなんとかついていけます。しかし企業Bは20点の仕組レベルです。90点を狙おうとするとかなり無理をしないといけません。20→90なので、経営コンサルタントもたくさん至らない点を指摘したり、高いシステムの導入を提案します。企業Bはその指摘やアドバイスに必死に答えようとしますが、途中で息切れして結果中途半端に終わってしまいます。これがよくある大企業出身者が経営コンサルタントとして独立し、企業規模が比較的小さい企業に三顧の礼で迎えられたものの、レベルの高すぎる指導によって失敗に終わる典型的なケースです。
こういう場合、どうすればよいのか。企業Aに対しては、90点を狙うコンサルティングで構いません。しかし、企業Bに対してはまず40-50点を狙うコンサルティングをすべきです。弊社は、様々な企業の規模の支援をさせてもらっているので、この企業規模に応じた適切なハードルの設定とそこまでの進め方に長じています。
例えば、以下のような感じです。
・データ分析をするときに、データベースの設計やデータ描画ツール、複数の切り口設計を導入する前に、エクセルでまずは簡単に見てみる
・業務運用のマニュアルを作る際に、管理項目を少なくしてまずは3つだけできる運用を目指す
・精緻なフォーマットシートを使うのではなく、気づいたことを手書きで残しておき、そこから少しづつ標準化を図る
・今回のテーマは支援している企業からすると優先順位が低いと思われるので、簡便に終える
・企業内部の個々の知見よりも、大勢の人が理解できるストーリーがボトルネックとなっているので、知見を形式知化する
企業規模と仕組レベルに限らずですが、まずクライアント企業の現状を把握し、その現在地に応じてコンサルティングを提供することが重要と考えています。全てが100点の企業はありません。20点の領域もあれば80点の領域もあります。30点と診断させて頂いた場合には、50-60点を目指すコンサルティングを行います。逆に、自らの実力が80点まで引き上げることしかできないけれども、クライアント企業が90点の場合、支援を行っても投資対効果が薄いため、支援を依頼されてもこちらからお断りします。また、自らが手に負えない/支援が不可能な領域が課題であることもあります。その場合はパートナーと組んで解決していったりします。
この状況に応じたコンサルティングを行えないと、コンサル側、クライアント側双方が不満足な状態になってしまったり、歯車が合わない結果となります。逆に状況に応じた支援ができると、達成までのスピードや取組み内容が地に足着いた形になり、着実にクライアント企業の実力アップに資することができます。この点を弊社霧海風は強みとして挙げていますし、経営コンサルティングを行う際にも最も重要な要素のひとつして留意しております。