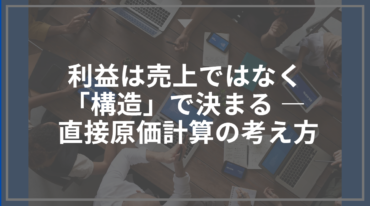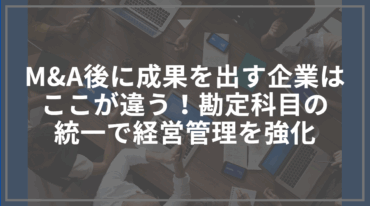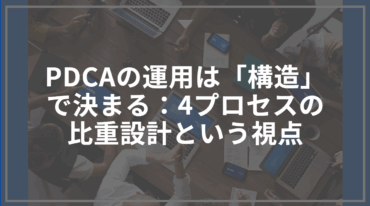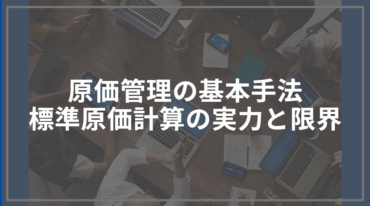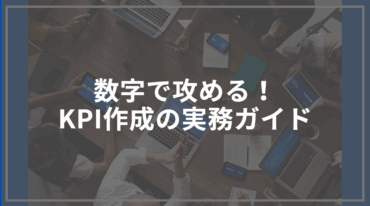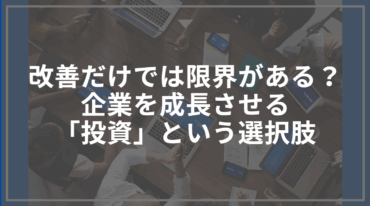今回は費用の固変分解による利益の試算を扱ってみます。費用は、企業の損益計算書の中に出てきます。材料費、労務費、経費、広告宣伝費、人件費、etc。損益計算書の中に出てくる費用は決算や税金の計算のために作られています。ここで、事業が成長したとき、すなわち売上が伸びたときに費用はどうなるのか、利益は?といった試算は、損益計算書に出てくる費用の勘定科目のレベルで行おうとすると曖昧にならざるを得ません。一度自社の損益計算書を元に、試算してみてください。売上が2倍になったら利益はどれぐらいになるか。すぐに計算して出すことは難しいはずです。そこで、費用を固定費と変動費に分けること簡便にそしてロジカルに利益を試算できるようになります。
固定費は、事業の売上が増減しても動かない費用、変動費は、事業の売上が増減したら変化する費用を指します。代表的なものを挙げます。
固定費:役員報酬、給与、福利厚生費、地代家賃、通信費、減価償却、保険料、支払利息 等
変動費:材料費、労務費、外注費、販売手数料、運送費、消耗品費、派遣費 等
まず損益計算書に出てくるこれら勘定科目の費用を固定費と変動費に分けます。変動費は、ある要素が動くときに、因果的に費用も動く、という意味です。例えば、売上を上げるために、必要な材料を買おう!となったとします。材料の量(kgなど)という要素が増えると、因果の結果として必要な費用も比例して上がります。一方で固定費は、売上が上がろうが下がろうが変わりません。家賃は売上が上下しても毎月同じ費用がかかります。
固定と変動で分けるときに、両方の性質が混ざっている費用が出てきます。例えば、設備の減価償却は固定費だけど、投資を追加したら固定費の水準は上がる→階段型固定費。通信費は固定だけど、通信料が一定を超えると変動的な費用に切り替わる→固定変動混在費。この場合、正確に状況によって場合分けしようとすると判断が難しくなるので、どちらの性質が強めかを実態に即して固定/変動のどちらかに判断します。
これで、売上-変動費-固定費=利益、が計算できるようになりました。ここから試算をするときのポイントは、変動費は比率で置き、固定費は額で置くということです。具体的には、売上100、変動費率40%、固定費30とします。この場合、利益は30(=売上100-変動費40-固定費30)です。この企業が売上200に上がった場合、どうなるか。売上200-変動費80(200×40%)-固定費30で、利益90になります。勿論、売上がどれだけ上がっても変動費率/固定費はそのままずっと推移するの?という最もな指摘はあります。ただ、一定の範囲内(難しく表現すると正常な操業圏)では、極めて簡便な式で精度が高い試算ができます。
この試算ができると、売上をどれぐらい上げれば利益が出るのか?利益を残すにはどれぐらい売上を下げても(=企業再生など)大丈夫なのか?変動費の材料費率をどれぐらい下げれば利益はどれだけ上がるのか、が誰でも説得力を持ってできるようになります。ここまで試算できるようになると、自社の戦略と連動して表現することができます。財務数値とビジネス実務が繋がります。是非、固変分解して利益を試算し、戦略とリンクさせて頂ければと思います。
補足ですが、固変分解をするとき、期末の棚卸在庫をどう評価するか、がありますが今回は割愛します。また固変分解の発展のCVP分析と共に取り上げようと思います。