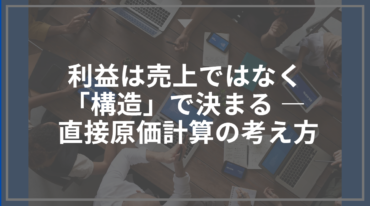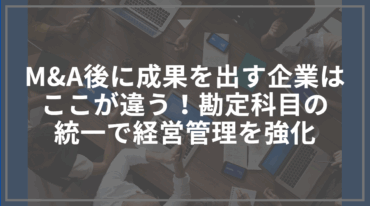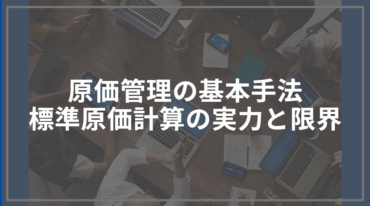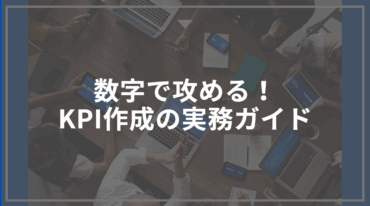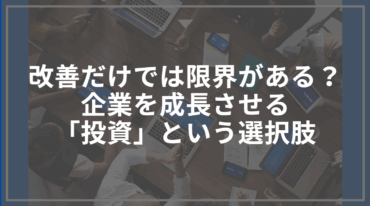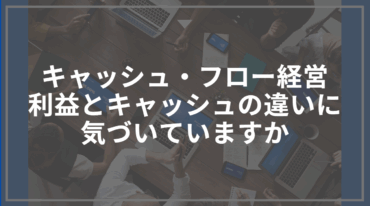PDCAサイクル、聞き飽きた方も多いと思います。10-20年以上前から知ってるし取組んでいる、と。しかし基本的だと思うことが意外にできていないことは多いと思います。実態としては実践できていない、と。そこで改めてPDCAサイクルを見つめ直してみましょう。まずPDCAサイクルとはなんなのか。業務の品質や効率を高めるために、業務をPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つのプロセスに分けて実行管理する業務管理の手法を指します。ビジネスにおける目標を達成するための手法として、古今東西で活用されている普遍的なフレームワークです。それぞれを細かく見ていきましょう。
Plan(計画)
目標を設定し、それを達成するための計画/到達するためのロードマップを立てます
Do(実行)
計画で立てた道筋とスケジュールに沿って粛々と実施していきます
Check(評価)
目標と道筋/スケジュールに対して、実施した結果どれほど進んでいるのか/遅れているか、を確認します
Action(改善)
目標/スケジュールに対して遅れている場合、方向性や活動量の軌道修正をして改善していきます
RePlan(再計画)
改善する中で、当初の計画の達成が難しい、目標の方向性を大きく変更する必要が出てくる場合、改めて計画を練り直します
この4プロセス(+RePlan)を繰り返していくことがPDCAサイクルとなります。
ここで、企業活動で行うPDCAサイクルでよくある失敗/成功パターンを示します。趣向を変えて面白く分かり易いように、PとDとCとAとRePlan(=R)を10回行動すると表現します。各プロセスの比重に注目ください。
失敗パターン
➀Dのみになってしまう/DDDDDDDDDD
猪突猛進、実行こそ至高と考える組織によくあるケースです。アイデアや計画に価値は無い、と実行に価値を置きます。しかし目標や道筋が各人であやふやであったり、振り返りや改善が無いため、上手くDが機能しているときはよいのですが、方向性を間違えて明後日の方向に突っ走ってしまうことも多いです。達成感は得られてしまうので、周りに指摘してもらう人がいないとそのままになってしまう危険性があります。
➁力作のPでD少なめ/PPPPPPPPPD
これは大きな組織になるほど陥ってしまうケースです。大きな組織ほど優秀な人は多いですし、管理部門も充実します。そうすると計画や目標を立てられる人が多くなってしまい、実行が少なくなってしまいます。また計画と現場が離れているため、計画と実行の温度感が大きく乖離してしまいます。そして計画立案者は計画を立てることに達成感を感じてしまいます。加えて、評価と改善を行わないまま翌年度の計画を立てるので、過去の反省を活かさずに惰性の計画になりがちなところも欠点となります。
➂評価と改善無し/PPPPPDDDDD
計画をきっちり作り、実行も十分に行うケースです。しかしながら評価と改善が一切行われないため、軌道修正が行われず、向かっている方向に近づいているのか/遅れているのかなどが不明なままです。まるで目隠しをしながら走り続けている状態です。計画と実行のバランスが一見取れており、上手く機能しているように見えます。それがゆえに気づきにくいという点も踏まえると➀と②よりも危険な失敗パターンと言えるかもしれません。
④Pの見直し無し/PPPDDDCCAA
4プロセスをバランスよく実施しているケースです。PDCAサイクルを適切に繰り返しています。但しRePlanがないため、大きな絵を描いたはよいものの、それを是としてずっと続けてしまっています。細かな軌道修正はCとAで行っていますが、大局観が失われています。例えば印刷された紙の需要は年々少なくなっているのに、その動向は無視して、細かな取引先に対する売上の計画はきっちり立てて評価/改善はしている場合などです。ターゲットとしている市場が安定している/成長している場合は良いのですが、大きな流れの変化が生じた場合に対応ができません。今一歩というところです。
成功パターン
➀マクロ/ミクロ目線で4プロセス+RePlan実施/PPDDCCAARR
市場の動向といったマクロな目線で計画を立て、ミクロの実行と評価改善を繰り返す、そして市場のマクロ変化を反映して再計画していくケースです。大局的視点と現場視点を繋ぎ合わせるとともに現場の実行と軌道修正もバランスよく行う。途中で変化が起こっても柔軟に対応し続けられます。この姿が本来のPDCAサイクルを最も体現しています。一点弱点としては、他のパターンよりDが少ないため、徹底がおろそかになるところです。今の時代、実行を徹底的に行うところにより価値が高まっています。状況によってはDを増やして対応することが必要です。
さて、細かなPDCAサイクルの中身というよりは、4プロセスの比重や考え方に焦点をあててみました。どのプロセスに比重を置いているか、なにかひとつにかたより過ぎていないか、を自社組織で今一度見直されてはいかがでしょうか。PDCAサイクルには、担当者決め、KPIとの連動、全社と部門の関係、情報共有など様々な論点も潜んでいますので、次回はその辺りも含めてお話いたします。