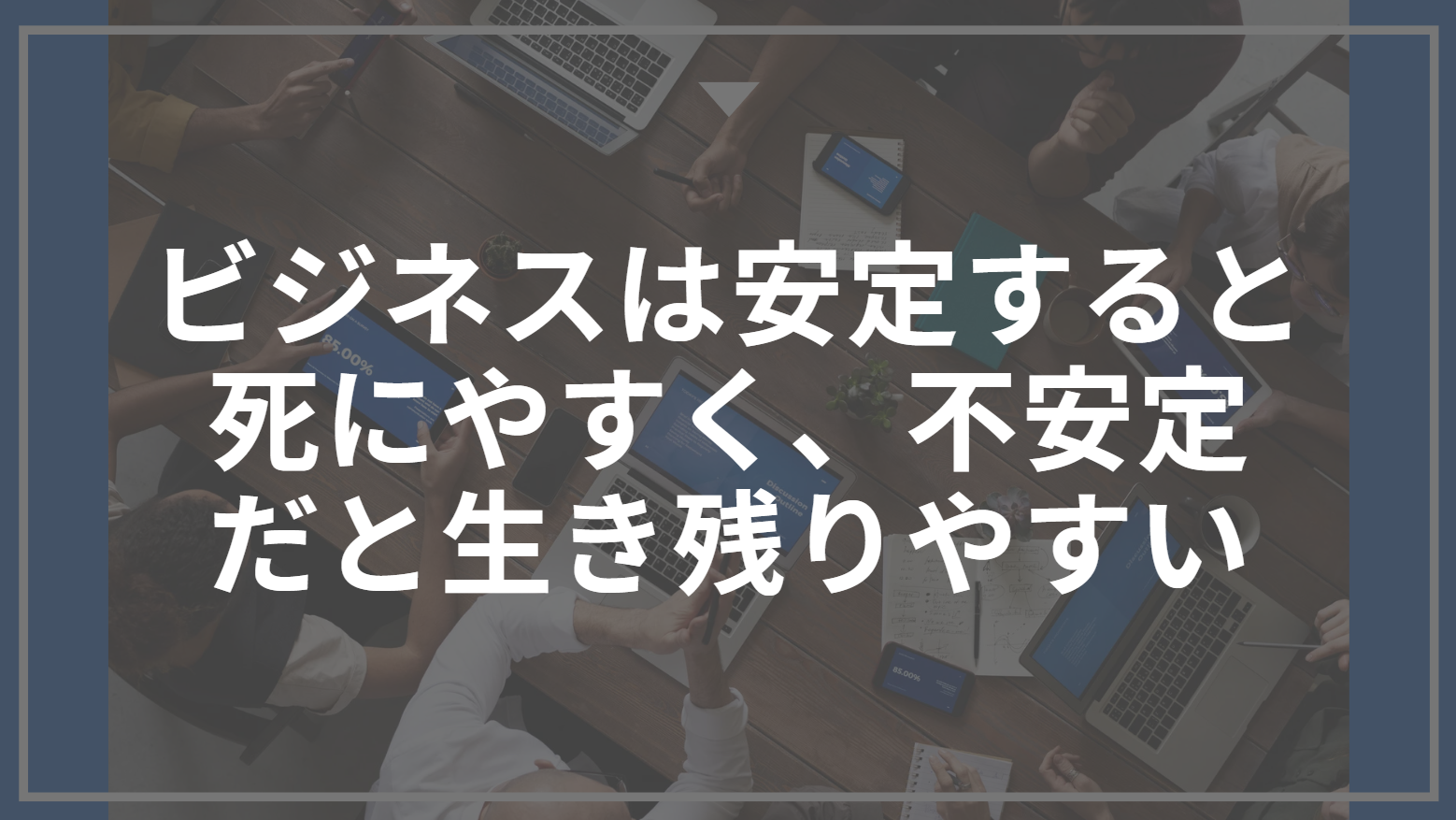今回はNVIDIAの経営を学びたいと思います。半導体メーカーであることはうっすらわかるが、はてどような企業なのか、というのは実はあまりよくわからない方も多いと思います。自社の経営に活かせる部分をNVIDIAを通して学んでいけたらと思っています。
NVIDIAとCEOの特徴
・1993年に創業した米国の半導体メーカー(本社はカリフォルニア州サンタクララ、シリコンバレー地域の都市)
・祖業は3次元グラフィックス用の半導体で、主な用途はゲーム、創業時から異色のビジネスを展開
・最も並列演算が得意な半導体GPUを1999年に世界初で開発
・CEOは創業者である台湾出身のジェンスン・ファンで、黒い革ジャンが特徴的、技術起点で並みの大学教授では太刀打ちできないほどAIに造詣が深い(リーダー気質の経営者かつ技術オタク)
・9歳で渡米、オレゴン州立大学を卒業し、半導体メーカーのAMDに入社して設計者として働きながら夜はスタンフォード大学の博士課程に通い、その後LSIロジックに転職。そして2人の仲間と出会い3人でNVIDIAを創業
財務・業績
・2024年6月に時価総額が世界トップ、2025年1月には3兆円を超える(3兆円超えはマイクロソフト、アップル、エヌビディアの3社のみ)
・時価総額2兆ドルから3兆ドルに到達する日数は、アップルが1044日、マイクロソフトが945日、エヌビディアが96日
・売上高1300億ドル(約19兆円)(2025年1月期)の9割が、データセンター向けのGPUで、営業利益率60%以上
・生産設備をもたない半導体メーカー=ファブレス(常に最先端の製造設備を更新する必要で固定費がかさむため)
ビジネスモデル
・ハードとソフトの両面で牙城を築いている
・ハード:TSMCとの密月の関係で最先端技術を活用したGPU(画像処理半導体)の性能が競合製品を上回っている
-GPUは大量のデータを同時に計算する並列処理が得意で、CPU中央処理演算装置は汎用の計算機で演算を次々に処理する逐次処理が特徴
-GPUはグラフィクス用の半導体で、ポリゴンを描画するために多数の座標の集合体を移動させたり回転させたりする=ディープラーニングの変数にどんな重みづけをするかの行列演算がAIに必要な能力に合致
-TSMCは、半導体の回路の性能を決める微細化の技術があり、10ナノメートル以下の微細化が可能な4社のうちの1つ(他は韓国のサムスン電子、米インテル、中国のSMIC)
・ソフト:CPUの計算速度を最大化させるソフトウェア開発環境のCUDA(クーダ)が開発者の標準プラットフォームになっている
-CUDAはNVIDIAのGPUを動かすために専用に設計されており、他社のAI半導体には適用できない
・少なくとも数年はAI用半導体で対抗馬が出ずに競争優位が続く可能性が高い
・90年代の半導体製造の主流は、米インテルのように設計と製造の両方を手掛ける垂直統合型であったが、NVIDIAはGPUの開発と設計のみを担当する水平分業型にした
-性能の優れた半導体を企画するのと、その半導体を実際に生産することに関連が無くなってきた
・GPUを利用するにはNVIDIAのソフトウェア開発環境のCUDAが必要。(pythonやPyTorchなど)開発者目線では垂直統合型にして参入障壁を築いているところがユニーク
・ハードとソフトの両方に多額の投資を行い、ソフトを無料にする代わりに、ユーザーをハード(GPU)に閉じ込める役割を担っている=プラットフォーマービジネス
-CUDAを利用するユーザーが増えるほどGPUの価値が高まり、ネットワーク効果を生み出す
・GPUとCUDAという競争力の高い土台に、製造業向けのアプリケーションを展開していくことでよりプラットフォーマーとしての性格を増しつつある(エージェント型AIの展開)
経営手腕・仕組
・3つの秘密
➀社内の情報流通性を高める独自の仕組
・CEO直属の幹部を60人にしている。一般的に管理限界は10人程度とされているがそれを大きく逸脱。なぜなら情報の価値を失わないために組織をフラットにする必要がある
・ピラミッドの改装を3-4階層減らす減らすことでコミュニケーションコストを削減し、情報が流通するスピードを上げている
・1対1のミーティングをしない、1対多とすることで60人とのコミュニケーションを実現
・創業者が箸の上げ下げまで口出すマイクロマネジメントの創業者モードが機能
②得た情報から市場の微かな兆しを掴む
・「T5T」社員はCEOはじめとする幹部に、その時に自分にとって最も大事な5つの事項をそれぞれ簡潔に書いて隔週でメールで送るようにしている(新たな市場への期待、足元の業務への不満、幹部への依頼)
・3万人いる社員からのトップ5をファン氏は生きた情報としてフル活用する
・事業の目標にKPIを設定していない、代わりにEIOFs(early indicator of future success)将来の成功のための早期指標)を代わりに採用している
-特定の項目や方程式は無く、注意を払うべき数字は各事業によって異なる GPUで高速化されたアプリケーションの種類数、などの弱いシグナル=早期指標
③その兆しを信じて一気に経営資源を投入する決断力
・mission is boss レポートラインは存在するが公式は組織図は無く、事業の使命こそ上司だという考え方
・PJのミッションを実現するために部署を横断してチームが立ち上がる、組織が臨機応変に姿を変え迅速に動けるようにする
・素早く動くため、中期経営計画や単年度の事業計画は原則として作成しない。
-数か月単位で技術のパラダイムが変わるため、誰がスケジュールを予測できるのか、といった考え方
・今日から全員がディープラーニングを学んでほしいと、AIの潜在的な可能性に気づいたファン氏から全社員に指示。トップの号令でミッションに全リソースを投入する一点集中経営
・人事面ではコンサルティング会社に近い、専門性の高い人材がそれぞれの分野の知見を持ち寄ってPJチームを形成する
カリスマ経営者 ファン氏とマスク氏の違い
・ファン氏はフラットな組織を志向し、マスク氏は直接的な対話を重視する。いずれもコミュニケーションコストを下げて伝言ゲームを避ける点で共通
・ユニークな仕事術も類似。ファン氏は朝一番にその日最も重要な仕事に取り掛かる、マスク氏は厳選した85%の仕事に全力で取り組むことで100%以上の成果が出るの信念
・ファン氏はなるべく解雇をしない、マスク氏は旧ツイッター社の8割を解雇
報酬や働き方
・エンジニアの平均年収は4000万円で、米アップルや米グーグルをしのぐ
-高い年収を可能にしているのが、譲渡制限付き株式ユニット(権利付与から4年後の権利確定までの間に株価が伸びたぶんだけ報酬が増える)
・テック企業でオフィス回帰がトレンドになっているにもかかわらず、完全在宅勤務を可としている
・レイオフが少ないという心理的安全性が従業員の満足度向上の一因になっている
・エンデバーとボイジャーの2棟からなる宇宙船のような本社オフィスは、できるだけ多くのエンジニアをできるだけ少ないフロアに集めることに腐心した設計
-アレン曲線=同僚が1.8mの距離にいる場合と18mの距離にいる場合でコミュニケーションの量が4倍の差があることを前提にしている、の考え方を活用
自社経営への活用
NVIDIAは売上19兆円、時価総額3兆円(2025年1月時点)で、超巨大な最先端テック企業の一端を見てきました。この企業の特徴をもとに、日本の企業組織でも活かせる点を整理したいと思います。テック企業の技術力自体を真似するのは難しいので、それ以外のビジネスモデルや仕組に焦点をあててみます。
➀自社の商流のうち、自社の強みに応じた立ち位置を明確にすること
・商流と関係者を可視化(調達→製造→販売→保守→付加価値サービス、調達先・顧客・提携先など)
・自社の強みとなる能力(設計力、営業ネットワーク、顧客データ、システム構築等)を特定する。
・強みのうち、模倣されにくい源泉を定義(例:独自データ、顧客関係、アルゴリズム、設計ノウハウ)し、そこを中心にビジネスモデルを作り上げる
②社内の情報流通の速度を高めること
・直接伝播できる対象を増やすため、1対多ミーティングを活用する
・物理的に接触を図れるようにフロア/席を近接的に配置し偶発的接触を増やす
➂KPIを極力絞り、市場の兆候を掴むものを重視すること
・KPIは3個程度に絞り、加えて売上よりも前段階の指標を追うことに注力する(web頁のインプ数、新分野でのPoC件数、開発者コミュニティでの発言数/資料ダウンロード数など)
④数値計画の作り込みに時間をかけない
・事業別や顧客別、単価や提案数など、変数を多く分解した精密な数値計画を立てることはやめて、ざっくりとした目標数値のみをかかげる
⑤従業員の働きやすさ/報酬設計に注力する(専門家集団が前提)
・フルリモートの容認+コア出社日を設けたハイブリッド勤務
・レイオフを極力行わない方針や失敗を許容する文化を作る
・企業の業績連動型報酬を設計する
⑥フラットで機敏な組織(専門家集団が前提)
・自律的に動けるように階層をできるだけ作らない/減らす
・決裁や承認のルートをできるだけ簡素にする
NVIDIAの経営を見て、幾つか自社の経営に活かせる部分もあったのではないでしょうか。市場の変化を速く読み、それに応じて迅速に自律的に対応する姿勢は取り入れていきたいものです。
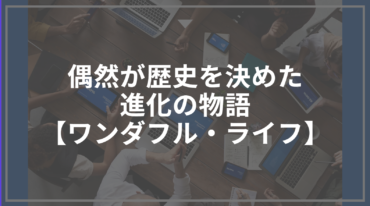
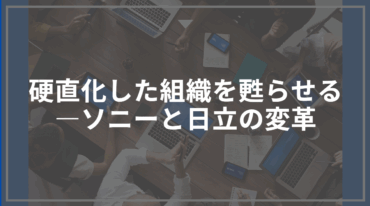
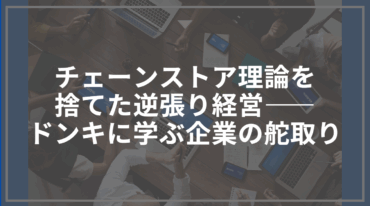
.png)
.png)