なぜ今、企業変革の学びが中堅企業にも役立つのでしょうか。グローバル競争の激化や市場環境の変化が早い現代、規模の大小を問わず組織は硬直化しやすく、変革を後回しにすると機会を失うリスクが高まります。今回は、戦後日本の高度経済成長を支えた総合電機メーカー、ソニーと日立の変革期を振り返りながら、組織が硬直化する状況でいかに立て直し、成長軌道に乗せたのかを紐解きます。両社の変革からは、組織の柔軟性を保つ人材方針や意思決定の仕組み、そしてトップのリーダーシップのあり方について、規模に関わらず応用できるヒントが見えてきます。
ソニーと日立は一見すると大分性格の異なる企業ですが、いくつか共通点があります。
・技術力を起点に事業を多角化している
ソニー:ウォークマン、プレステ 日立:鉄道、電力システム
・グローバル企業である(売上の大半を海外から得ている)
・グループ経営の大規模さ
多数の子会社関連会社をもつ 金融、半導体、IT、サービスなどコングロマリット
・業態転換と選択と集中(家電メーカーから事業構造をシフト)
ソニー:金融、ゲーム、音楽、映像
日立:重電、インフラ、ITサービス
そして、変革に立たされた時期をベースに両社の変革の要諦を簡単に紐解いていきたいと思います。
ソニー
背景:テレビ事業の不振が続き、ソニー全体も2012年3月期に▲5,000億円の赤字で経営危機に直面
変革期:2012-2018年
CEO:平井一夫氏
結果:営業利益7,349億円
日立製作所
背景:2008年のリーマンショック後に7,000億円超の赤字を計上し、立て直しが急務。前任の中西宏明氏が選択と集中で基盤を整備
変革期:2016-2021年
CEO:東原敏昭氏
結果:営業利益7,495億円
それぞれの企業の変革を紐解こうとすると、CEOに着目するのが良く、トップ2人の特徴や行動を中心に整理してみました。
ソニー
平井一夫氏の特徴
・リーダーとしてのEQ(心の知能指数)の高さ
・日本と海外生活の往復による異邦人さ
・エレクトロニクスが本流事業の中で、音楽/ゲームの異端のキャリア
平井一夫氏の行動・指針・言説
・常に異なる考え方に触れて異見を経営に取り入れる
・方向性を決める。決めたことに責任を取る
・もし部下の選挙であなたが当選する自信はあるか?
・クリエイター・ファースト
・商品と会社のポジションの明確化 ➡ PS3はコンピュータではなくゲーム機だ
・肩書で仕事をするな
・まずは成功した状態をイメージせよ
・リーダーは自社商品/サービスの一番のファンであれ
・テレビ事業の量から質への転換 ➡ 韓国・中国勢との際限のない価格競争を避ける
・2015年中計で売上高を目標に掲げるのを止める
・異見を言ってくれるプロを傍に置く
・危機には燃えるが平時は人に任せる
日立
東原敏昭氏の特徴
・歴代CEOは東大工学部卒か日立工場の出身者だが、設備の制御系システム開発する工場の出身と傍流
・幅広い分野での現場経験/トラブル解決が豊富(火消しのファイアマン)
東原敏昭氏の行動・指針・言説
・事業部別採算のカンパニー制はサイロ化しやすく変革の足かせになっている
・BU制を導入し、典型的なトップダウン体制を敷く
・流れる水は腐らず、組織の硬直化が大企業病の原因である
・社内外/年功序列を問わず必要な能力を持つ人材を登用する
・自律分散型グローバル経営
世界の拠点が本社の意志決定に基づくのではなく共通理念のもとに其々自律的に事業展開していく
-均質性 企業理念の共有
-制御性 独自の判断で自立して事業を遂行
-協調性 地域間の影響を受けないように
・共感力/利他の心が大切 ➡ 顧客の考えを理解し価値は何かを考える
■両者の共通点、相違点
共通点としては、構造改革やガバナンス改革を行う中で、大企業病の組織の硬直化の打破に心を砕いているように見えます。また平井氏の「肩書で仕事するな&異見を募る」、東原氏の「年功序列を問わない必要な人材の登用」といった非常時の人材の方針も似ています。相違点としては、音楽/ゲームの傍流の事業かつ国際色が豊かな経験からトップになった平井氏は、自身1人だけの経験や知見では変革を成し遂げられないと考え、周りを巻き込む思考が強く感じられます。一方で制御系システムの現場トラブル解決が得意な地に足のついた経験が豊富な東原氏は問題を直視し、業務の流れを描いてボトルネックを解消するところに腐心している思考が強く感じられます。自律分散型グローバル経営の3つの視点もシステム系の考えが色濃く出ています。
■変革に向けた教訓
変革の期間では、ソニーの売上7兆円、日立の売上10兆円と日本を代表する巨大企業でした。余りに大きすぎるため変革に向けた教訓が一般的に通用しない場面もあると思います。しかしながら、人が50-100人集まれば立派に事業が複数生まれ、マネジメントの難しさも発生するはずです。そうした前提に立つと、やはり歴史が長くて大人数いる企業は組織が硬直化します。ここはローテーションや組織を壊してもう一度ゼロから作り直す、及び新しい血や外部の血を入れることで腐らないようにするというのが良策ではないでしょうか。またそうした構造を変えたとしても現場が聞く耳を持たなくては意味がありません。年功序列に縛られずにあるべき人をあるべき職位や役割に任命したり、全く異なる意見を自分の信念と相いれないとしても取り入れたりするのも必要だと思います。結局のところ、企業変革の成否は、内部の人材と意思決定のあり方にかかっていると言えるでしょう。
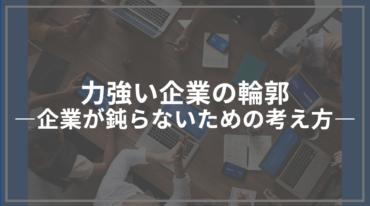
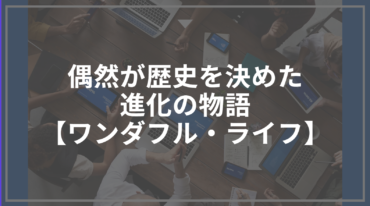

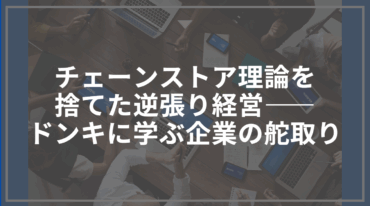
.png)
.png)