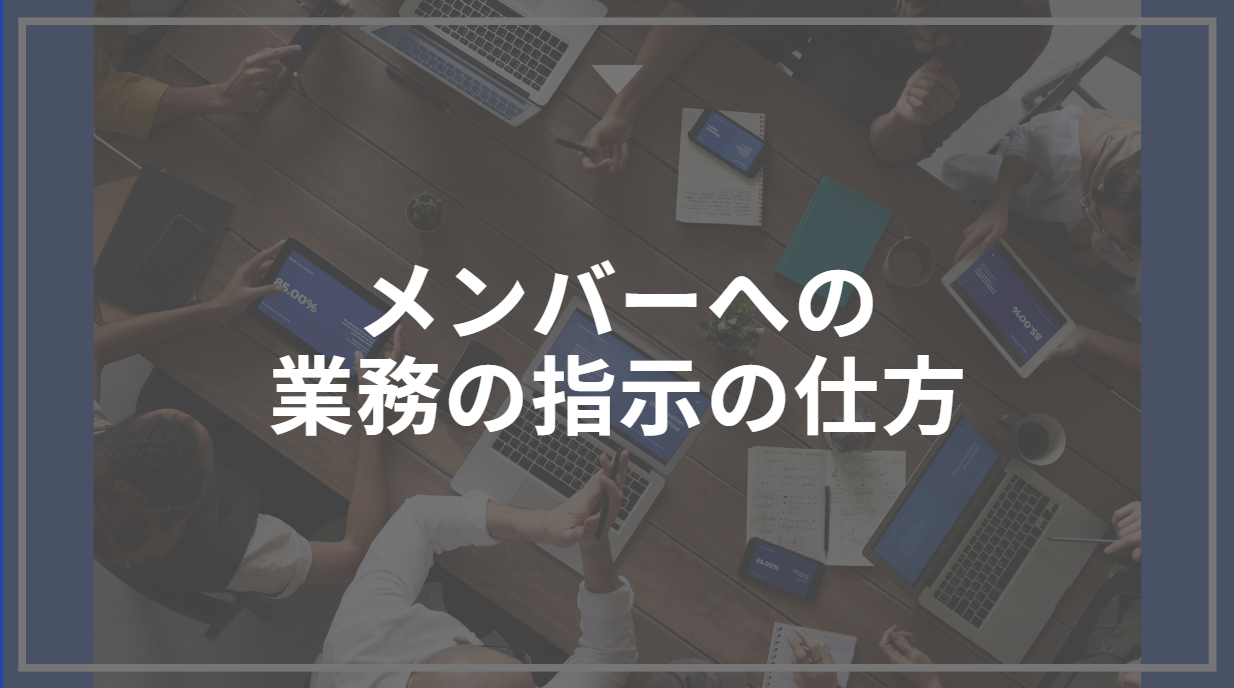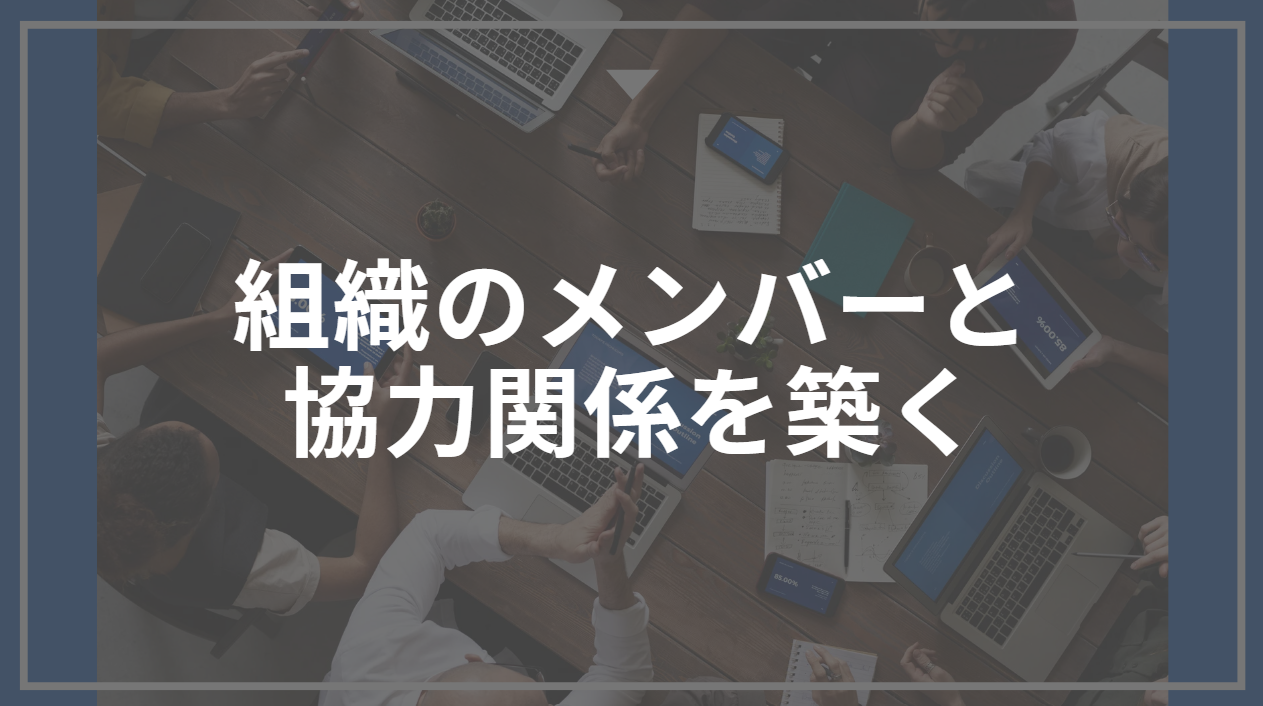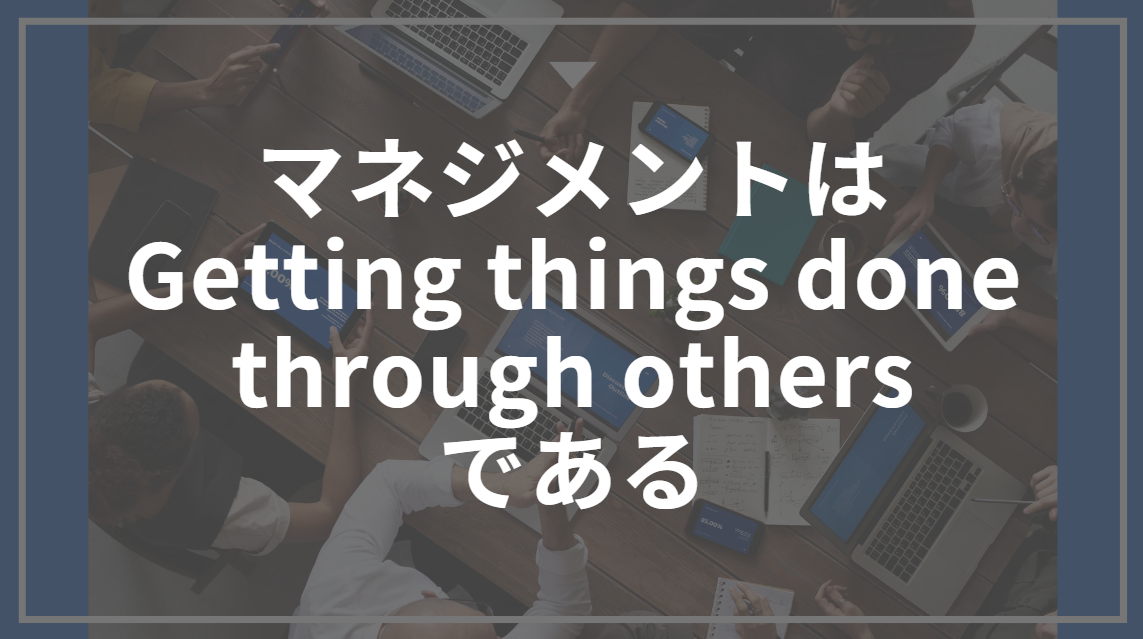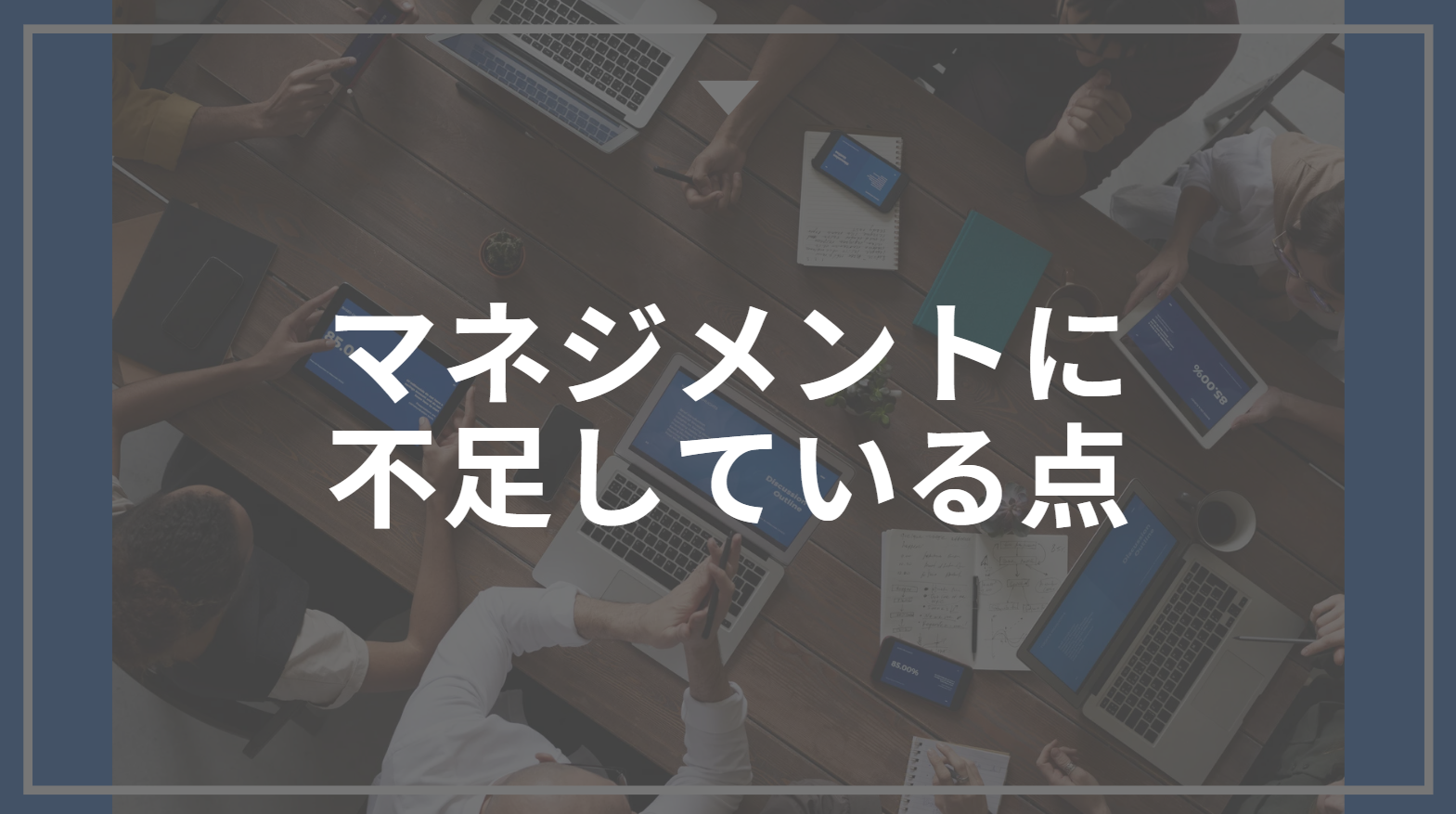組織に属していると、必ずといっていいほど行うであろう「会議」。2人以上で時間を拘束して話し合うことがあればそれは会議と言えます。(業務の手順などを2人で立ち話で擦り合わせする、といったことも広く捉えれば会議に含まれます)ほぼ全ての人が会議に関わったことがある中で、意外と会議の作法を学ぶことは少ないのかな、と思います。そしてあまり意識されることはないのですが、会議には多くのコストがかかっています。例えば10人が参加する2時間の会議があったとします。平均すると10人の給与は時給で5,000円とします。すると、10人×2時間×5,000円/時=100,000円になります。たかが2時間と思うかもしれませんが、10万円のコストを要していることになります。こう捉えると目的もなくただ集まって雑談しているだけでは会議として上手くない、となり生産性も悪く改善が必要なことがわかると思います。(交流を深める目的での雑談タイムなら別です)
そこで1)良い会議とは、2)会議で必要な要素、について触れていきたいと思います。
1)良い会議とは
まず会議の最終的に目指す姿とはなんなのかを整理してみましょう。理想が見えなければどんな会議がよいのか想像もできないはずです。想像もできなければ目指すこともできないわけです。
良い会議とは、小難しい定義になりますが以下になります。
参加者の意見を(設定時間以内に)引出して、目標に向けた意思決定ができること
会議の目標がきちんと定まっており、その目標に対して参加者全員が意見を喋ることができている。会話の中で、新しい気づきや化学反応が起こって物事が前に進んだり参加者の認識が共通になっている。意見が異なるときも、前向きで建設的な議論が行われている。そして(決められた時間の)会議が終わると目標に向けての次の行動が決まっている。
こんな姿が良い会議と言えます。逆に、以下のような会議は悪いと言えます。
・特定の人ばかりが喋っている
・喋っていない参加者がいる
・会議で到達する着地点がない(どこまで話せば終わりかわからない)
・会議が間延びしていつ終わるかわからない
・議論しても一方的に非難される
・話がいつも脱線する
・人によって認識がズレたまま会話している
上記のような特徴を持つ悪い会議を反面教師にしつつ、良い会議の状態に近づくように意識していきましょう。
2)会議で必要な要素
次に、良い会議を目指す上で、必要な要素を6つ取り上げてみたいと思います。この6つを押さえることで良い会議に繋がります。
➀目的
会議は何のために行うのか。意外にココが抜けています。しかしいざ何を目的にするのかと言われても難しいと思います。そこで幾つか類型化します。一般的には会議と捉えられていないものも混ざっています。
A共有・・・進捗や取組みの共有のみを行う目的です。
B案出し・・・新規事業や新しい施策を始める場合に、アイデアを出来るだけ多く募る目的で行います。
C議論・・・A案かB案かどちらがよいかを意見を出し合って決めていく等の議論が目的です。
D意思決定・・・報告を受けて、施策を続ける/やめる、人を増員する等の意思決定が目的です。
E儀式・・・皆で集まり作法に則って式を行うことで、一体感や士気の向上に繋げるのが目的です。
F交流・・・ランチ会や部署横断会での雑談や共同作業を行い、交流を深めることが目的です。
G研修・・・知識の習得や他部門の知見を学ぶことを目的とするものです。
これ以外にも目的はあると思いますが、会議は上記のような目的に沿った形で行う必要があります。議論のはずが共有に終わったり、意思決定のはずが案出しで終わったり。よくあるのは、共有の目的で会議を行うも、集まって会議をする意味はあるのか?といった事象です。メール配信でよかったり、短時間の会議で済ませばよかったりします。もちろん全員で目線を合わせて共有するのが重要、ということもありますので、目的を今一度振返りましょう。
➁ゴール/目標
会議の着地、到達点です。どこまで会議を行うのか、と言い換えてもよいかもしれません。これも数値的に目標を決められるわけではないので、意外に難しいのですが、幾つか具体例を記載します。
・資料の10Pまで参加者で同じ認識で共有できていること
・XXXの議論が開始できていること
・XXXの議題が可か不可か決められていること、もしくは決められる状態になっていること
・次回までの各人のタスクが確定し周知できていること
・XXXの件について、アイデアが1人10個出ていること
定性的なゴールが多いので、明確にここまでやれば完了と言えないのですが、目安にはなると思います。可否まで行かなくても、議論が開始できているから今日はここまででOKだな、とか。こうした目標を設定することで、どんな議題がいいのか、時間配分はどれぐらいが適切か、誰に参加してもらえばよいのか、どれぐらいの頻度で開催すべきかなどが具体的に浮かんできます。
➂日時/頻度/参加者
会議の日程をいつにするのか、所要時間はどの程度か、1回で終わらない会議ならばどのぐらいの頻度で行うのがよいか、参加者はどの程度必要か、といったことを設計します。一般的には、議論を活性化させる、及び参加してるだけの人がいる/長時間で場が停滞してくる、のを避けるため、7人以下で2時間以内の会議が適当です。企業によっては45分以内厳守、30分しかNGなどあると思うので場合に応じて設定下さい。また、1回で会議が終わらないことも多いので、月1回ペースなのか週1回なのかといったペース配分も設計することになります。参加者は、議題や目標に応じた適切な人選が望ましいです。webMTGだとそこまで気にならないですが、全く関係の無い人が聞いておいた方がよいという理由だけでたくさん押しかけて参加すると、場が停滞する、視線が多く喋りにくい人が出てくる、などがあるので気を付けてください。
④議題/時間配分
時々目にするのは、議題が全くない会議。立ち話や雑談、簡単な擦り合わせ会議なら不要と思いますが、例えば5人集まって1時間となると、議題は必須です。どんな内容で会議を進行してくかの道しるべになります。そして議題はあるが時間配分が無い会議も珍しくありません。往々にして決めた時間配分はズレることが多いのですが、目安としてどの程度の時間を要するのか(ゴールに達成するのに必要な時間と言う意味です)は存在している必要があります。議題と時間配分はセットで表現します。
例えば、➀前回の振返り 5分 ➁スケジュールの確認 5分 ➂XXXの議論 30分 ④進捗の確認 10分 ⑤振返り 10分 などです。
⑤纏め
④の最後にも書きましたが、振り返る纏めも必要となります。人によっては必須とまでは言わない人もいますが、議論が輻輳したり、大人数参加している場合は、認識のズレを防ぐために時間を取って行うことがあります。会議で行ってきた議論や出た話題を、ざっと要約して振返ります。AI議事録で文字起こししていればそれをベースに画面などに映して全員で確認するのも良いと思います。こんな話が出ましたよね、次回までにこんなこと確認する必要がありますね、などを口頭で確認していきます。
⑥決定事項とネクストアクション
会議とは最終的には意思決定に繋がらなければならないので、決定事項もしくはネクストアクションがあるはずです。(全くそれらが無い会議もありますが、次回の会議に持ち越して議論、などのケースでしょう)ネクストアクションとは、誰がいつまでに何を行うのか明確にすることです。決定事項とは、この案はXXXの理由で却下とする、XXXのテーマは部門横断で検討することとする、といったことです。決まったことを明確に言語化して残すことが重要です。少なくとも参加者には決まったことが明確にズレなく共有されていなければなりません。これを積み重ねていくことで事業活動を前に進めることができます。
いかがだったでしょうか。良い会議を目指して、会議に必要な6要素を満たせば、充実した会議を開催し、劇的に生産性が向上すること間違いなしです。いきなり全てに取組むのは難しいとしても、ひとつずつ日々の会議で取り入れてみてはいかがでしょうか。