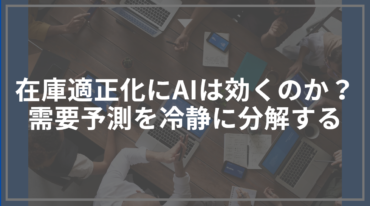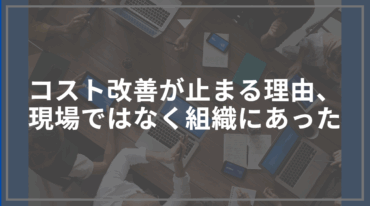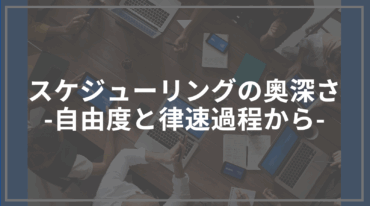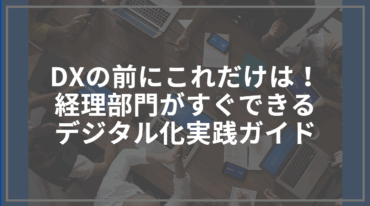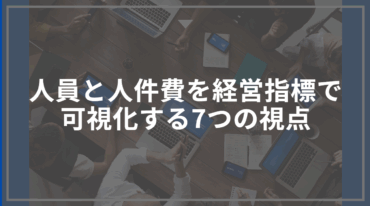今回は、Difyを使った業務効率化を扱います。数年前だとRPAを用いた効率化が流行していました。定型的なPC業務であれば、ロボットが代わりに自動で処理をしてくれます。しかしRPAロボットを多く作りすぎたり、安易に設計書が無い野良RPAを作り過ぎたがために、保守対応やトラブルで意外に対応負担が増してしまっているケースも散見されました。時代は進み、今は生成AIを挟んでかつローコードの効率化の方がより高度なことができ、かつ容易に行えることとなりました。そのツールとしてDifyを取り上げたいと思います。
今回、Difyの環境設定や操作方法、詳細の設計については一切触れず、Difyの概要と何ができるのか、を中心に書いていきます。
■Difyとは
生成AIを活用したアプリケーションを簡単に作成することができるプラットフォームです。生成AIであるchatGPTは便利ですが、多種多様な業務や組織で標準化された利用には特化されていません。個々のニーズに応じて言語モデルを最大限活用するためには別途アプリケーションの開発が必要になることがあります。しかしアプリケーションの開発にはプログラミングスキルが必要になり、開発するにも時間がかかってしまいます。そのような場合に最適なのがDifyです。プログラムをほとんど書くことがなく(=ローコード)レゴブロックを組み立てるような直感的な操作で生成AIアプリを開発できます。業務を一番理解している当事者自身が作れるようになることが重要で、外注開発では使いにくいところも自分で自由に修正したり新機能を追加できるようになるところが良い所です。
■Difyの必要性
chatGPTは多くの人々を魅了する特長として、汎用性の高さと使い易さがあります。質問への回答、文章作成、コーディング支援、翻訳など様々なタスクを1つのモデルで行うことができます。しかも特別な操作方法を覚えることがなく、チャットという多くの人に馴染みのあるインターフェースで自然に利用することができます。このような使い易さと高い処理能力により爆発的な普及に繋がりました。
しかしchatGPTなどの大規模言語モデルを使う場合には幾つか課題があり、
➀ユーザー数あたりのコスト(20-30ドル/月)
ユーザー数毎に契約しても利用頻度にバラつきがあれば非効率な支出となってしまうことがあります。
②データプライバシー
ユーザーが入力した情報が必然的に言語モデルを提供する企業のサーバーに送信して学習される=機密情報や顧客の個人情報の情報漏洩のリスクが懸念されます。
➂運用ワークフロー
実際に具体的な業務に適用する際に、chatGPTを使って議事録を取ろうとしても、音声ファイルを別ツールで文字に変換し、議事録形式に整形、社内クラウド上に保存など、付随する業務が発生します。ここは手作業になるため、言語モデルの効率化効果を相殺してしまう可能性があります。
があります。
Difyであれば、
➀APIを活用した従量課金制を採用でき、利用料に応じた支払いが可能です。
②MicrosoftのAzure Open AIなどの信頼性の高いクラウド環境を利用することができデータプライバシーを守って言語モデルの活用を進められます。
➂単純に言語モデルが利用できるだけではなく、言語モデルを利用することにより発生する付随した処理を行う機能も幅広く提供することができます。例えば、Googleスプレッドシートに入力したものをchatGPTに飛ばし、その出力結果をまたGoogleスプレッドシートに記載するといった、通常であれば手作業が入るものも、自動的に実施することができます。
■Difyでできる業務効率化
具体的にDifyを用いてできる業務効率化の事例を紹介していきます。Difyの詳細な機能は割愛し、概略でどんなことが出来そうかを想起できる点を重視しています。
➀標準レポート生成アプリ
業務レポートを各担当者がそれぞれ作る場合に、文章の文体がそれぞれ違ったり、異なる形式で入力したり、項目の記入漏れが生じたりします。そこでDifyの変数機能と言語モデルを組合わせることで、必要な情報を収集し、定型的な入力フォームも併せて用いることで、統一された読み易い形式のレポートを出力できます。
②Q&A自動生成アプリの開発
仕事で企画や施策の説明資料などを作成した際に、想定質問と回答を用意できると周知した後の利用者が安心です。そこで、資料として作ったPDFファイルのテキスト部分を抽出し、テキストに記載してある情報を元に、簡潔な内容に変換した上で質問と回答の形式にして出力できます。
➂顧客のアタックリスト作成
法人営業を行う際に、営業を行う先の顧客リストを作成します。そのリストの作成において、企業の事例紹介ページのURLをもとにスクレイピング探索を行い、各事例や人物(担当部署、氏名)のテキスト情報を取得して一覧化して出力ができます。表記のゆれが生じても、生成AIが文脈的に解釈し自動的に同一の固有表現で統合することも可能です。
④テキスト分類による感情分析
SNS投稿などから、商品についてのコメントを分析する場合がマーケティングのタスクとしてあります。ある該当商品に関わるSNS投稿を自動で収集し、ポジティブ/ネガティブ/中立に分類した上で、結果を出力できます。文脈上の単語の重みづけや単語間の関連性を評価できるモデル(Transformer)のおかげで好意的・否定的なモノを区別して抽出できます。
⑤サムネイル画像の生成
ブログやセミナー、動画などで、一番最初に目にするサムネイル画像を作る場合です。記事内容を作った後に、記事内容をAIに理解させたうえで、記事にふさわしいタイトルとサムネイルが作成できます。単純な生成AIによるtext to imageではなく、プログラミング言語のpythonの画像処理ライブラリと生成AIをDifyで組み合わせた、再現性と実用性の高い画像生成を実現できます。
※社内の情報を検索する場合や最新のニュース参照の場合は、通常の生成AIでは取得ができないため、RAG(検索拡張生成)という技術も組み込んでDifyを構築するケースもあります。
今回はDifyの技術的な中身の解説よりかは、実現できることに焦点をあててご紹介してきました。上記の5つ以外でも、活用シーンはたくさんあります。とはいえ、Difyは現場ですぐ構築できるものではありますが、Dify活用前提で業務の効率化を図るのはあまりよろしくありません。組織的に業務を改善するのであれば、どの業務をDifyで改善するかに合意をしてから改善するのがよいと考えます。もしくは組織で共通的にDify活用する業務と、個人の裁量でDify活用する業務とを切り分けて運用するのが吉と考えます。しかしながら、人手不足が深刻化する中で、生成AIやDifyを使った業務の負荷減少は大きな効果を発揮すると予想されます。