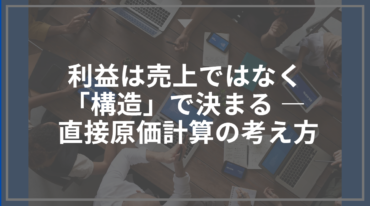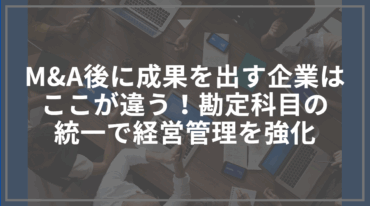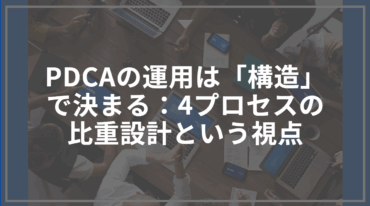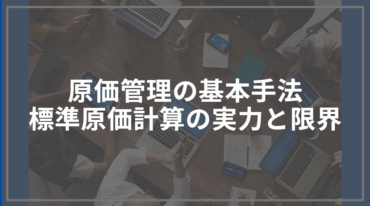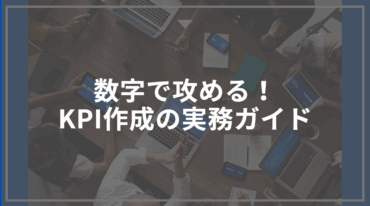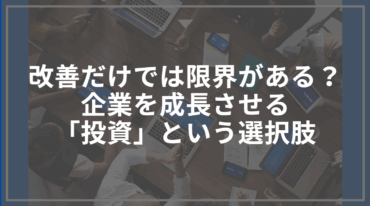測定できるものが必ずしも測定に値するもであるとは限らない———
測定できることの大部分は重要ではない。数えられるものすべてが重要なわけではなく、重要なものすべてが数えられるわけではない———
測れないものは改善できない、測定できるものはすべて改善できる——-
今回のテーマは測り過ぎな世の中、です。最近では、定量/定性のデータがデジタルに取得できる範囲が昔に比べて格段に広くなってきています。webサイトの回遊、営業の訪問記録、工事修理の証拠、リアルタイムの設備故障、人流、人々の感性、X投稿のテキストetc。そのため、測定できることは測定に値するということなので、全てKPIで管理しよう、という流れになります。しかし、その流れに警鐘を鳴らす話となります。そこで、測定項目を際限なく増やすことによる悪影響を列挙してみます。これによって如何に測りすぎがよくないことかを実感できると思います。
①測定対象に集中することで目標がズレる
測定実績の結果によって人の進退や評価が決まる状況になっている場合、その人はその対象の実績を上げることだけに集中する。その際、対象の周辺にある測定されないがもっと重要な項目を無視することになる。例えば強引に売上を達成して顧客の笑顔や満足度は無視するといったこと。測定という手段が、組織の目的にすり替わってしまう。
②短期的に物事を観る観点の増幅
測定するときに、基本的には短期的な目標が優先される。遠い将来や周辺への影響は除外されてしまう。毎月の業績は悪くていいから、今年終わりの業績は高めよう、なんて管理者は存在しない。まるで畑で収穫できる栽培限界を超えて作物を育成してしまい、長期的に土地を疲弊させて将来の収穫がダメになってしまうようなことが起きてしまう。
③測定基準の計測コスト
デジタルデータで計測が容易になったとはいえ、測定項目が多くなればなるほど、取り纏めや処理、報告の事務コストが多くなる。また、測定結果を確認する側も目を通す時間が長くなる。本来為すべき目標や生産性に貢献しない活動が多くなってしまう。
④規則の洪水
数字の改竄や不正、目標ずらしなどによる測定への不穏な性悪説の動きを止めるために、組織は洪水のようにルールを作って流布する。この数字を計上するときは計上時点で行うこと、この顧客は外してから計算すること、etc。そのルールに従うために組織の能率はどんどん鈍化していく。
⑤リスクテイカーの阻害
短期主義が奨励されることによって、まだ不明瞭で不完全なビジネスに対するリスクテイクをくじいてしまう。まだ出口が見えない新規ビジネスは、短期的に測定すると成果はほとんどゼロになる。成果がゼロな活動は止めてしまえ、となる。そうするとリスクを取って物事にトライするのは馬鹿馬鹿しくなってしまう。
⑥協力の抑制
個人や、集団であっても実質個人の積み上げに対しての測定と評価である場合、測定できない個人間の協力を促す動機が減退する。協力や支援は生まれずに競争が促進されることになる。競争だけなく、足の引っ張り合いや邪魔したりする最悪の状態が起こったりする。協力しても評価されないのであれば当然の帰結といえる。
これだけの悪影響を眺めると、測りすぎが最悪の結果を招く、ということがおわかり頂けたかと思います。次回は、測定を行うかどうかの判断リストを見ていきましょう。