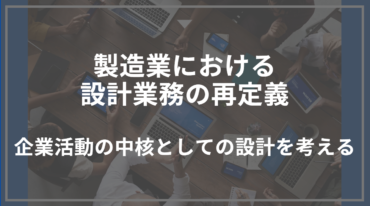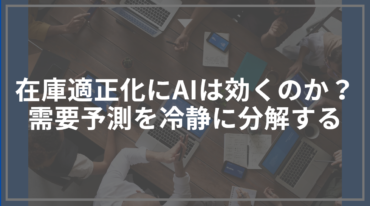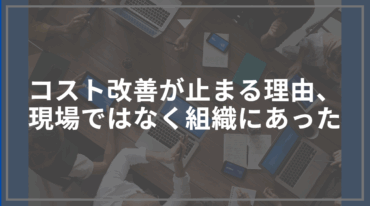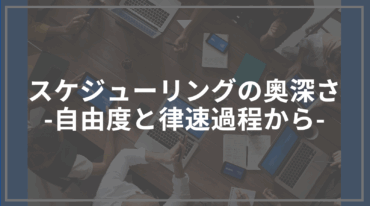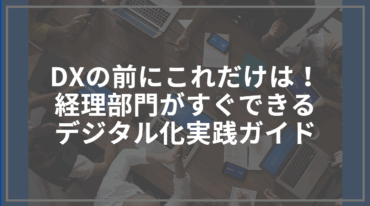業務の効率化を図るには、便利なツールの活用が欠かせません。今回は、RPAを取り上げます。ロボティック・プロセス・オートメーションの略称で、業務をロボットに代替させることで生産性を向上させるソリューションです。「ロボット」といえば、工場の生産現場で物理的に活躍するイメージですが、RPAのロボットは、オフィスのホワイトカラー業務を代わりに行うデジタルなロボットのことを指します。
日本でRPAが注目され出したのは2016年後半ごろからです。新型コロナウイルスに端を発したパンデミックによりテレワークを強いられたことが急激なRPAニーズ拡大に繋がりました。そして今後も市場規模は伸びると言われています。市場調査/コンサルティング会社のGrand View Research社の資料によると、2022年に23億ドルとされた市場規模は2030年までに308億ドルまで達すると予想されています。https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-robotic-process-automation-rpa-market
RPAはホワイトカラー業務を代わりに行うといっても、何に使えるのかのイメージが湧かないと思います。端的に言うと、費用対効果の面から、「システム化には至らない業務」、です。エクセルやwebツールを用いて人手で処理するには手間だが、システム化するまでの煩雑さではない。システム化の投資と見合わない手間。そうした業務が対象です。そのため、システム化する箇所とRPA化する箇所を上手く見極めて使い分けることが必要です。RPAで自動化できる業務は、具体的に言うと、「PC上のルール化された定型業務の自動化」、になります。PC上でのエクセルやワード、webサイトなどへの入力・登録、作成・出力、集計・加工などの業務が対象です。エクセルの数字入力の転記でRPAを用いたりすることが多くありますが、よく聞かれるのが、エクセルマクロとの違いです。エクセルマクロは画面操作をレコーディングして自動化できますが、エクセルだけに閉じています。一方で、RPAはエクセルに限らず、outlokkやweb、基幹システムなどPC上で行う様々なアプリケーションを跨いだ操作記録が可能になります。ここがマクロとRPAの違いです。
RPAはDigital Laborと呼ばれており、デジタルなアシスタントの位置づけです。アシスタントなので、自動化できる作業はロジカルに厳格に定義できる定型作業に限られます。例外処理や複雑な意思決定はできません。但し、人が行うよりも正確に、高速に、かつ休憩が不要で24時間作業ができるため、生産性が向上するとともに、人が行う際のミスや、検証の時間や負担も減ります。RPAは、ローコードで開発できるものも多く、比較的簡単に導入が可能です。ツールによってはプログラミング不要で組めるものもあり、未経験者でも利用可能な設計となっています。
以下のメジャーなRPAツールは、簡易型→ローコード型→コーディング型に大別されます。
①WinActor
簡易型。プログラミング知識が不要で、操作記録やGUIを使ったシナリオ作成が可能。
②UiPath
ローコード型。ドラッグ&ドロップで簡単にワークフローを作成可能。複雑な業務ではコーディングも必要になる場合あり。
③Automation Anywhere
簡易型+コーディング型。初心者向けの直感的な操作と、上級者向けのスクリプト機能を提供。
④Blue Prism
コーディング型。開発にはある程度のプログラミングスキルが求められ、エンタープライズ向けの高度な自動化に適合。
更にデスクトップ型かサーバー型か、などの検討も必要になってきます。
RPA導入で失敗している企業の例だと、保守・運用や統制・運用ルール(運用環境、管理ドキュメント、障害管理やセキュリティなど)、ロボット管理の面を軽視しているケースがあります。エクセル/ワードなどのツールと違って、簡易的ではあってもコーディングやフローを設計しているため、導入後にメンテナンスが発生します。また運用する際の社内ルールの整備や教育も準備していく必要があります。これらの点も踏まえてRPAの導入を考える必要があります。
導入後の運用など考える必要がありますが、RPAは生産性向上にパワフルな効果をもつツールです。適切に活用できれば成果をもたらしてくれるに違いありません。