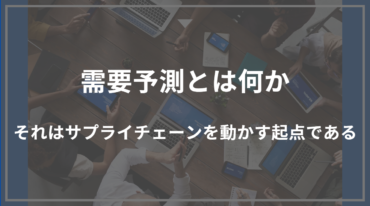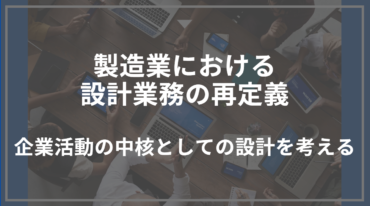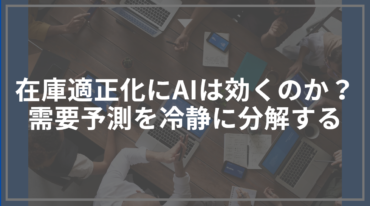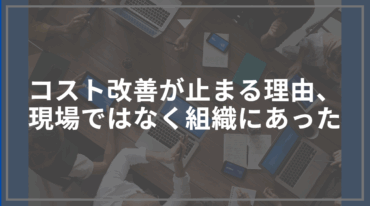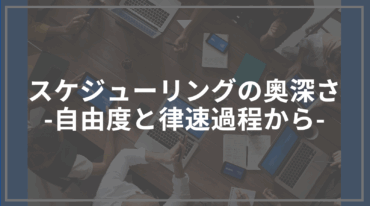今回は、主に製造業での資金繰り改善に直結する在庫適正化の話を取り扱ってみます。
在庫を削減しても直接損益に貢献しないため、適正化の取組みは一般的に劣後しがちです。しかし過剰な在庫はキャッシュが損なわれていますし、過少な在庫は緊急対応や欠品による機会損失を生み出してしまいます。通常、企業では欠品を恐れて多めの在庫を保持しようとする思考に陥ります。自らがお金を出して購入したものではないため、キャッシュが減る感覚を感じづらく、多めに持っておいても誰も困らないから、、というのが一つの原因になっています。
損益に影響しないと言っても、ムダな資産が膨れ上がることは、企業の資産効率の観点からまずい、ということが徐々にわかってきます。そこで資産効率で大きな比重を占める在庫の適正化に着手することになります。ただ在庫の適正化を図ろうとするとき、オペレーションの話に終始してしまい、在庫適正化に失敗してしまうケースが多発しています。例えば、次の例があります。製造リードタイムを短縮して過剰な在庫を持たなくても営業の要求に対応できるように業務の仕組みや情報システムを変更。しかし、販売計画が粗く、予定より低めの生産量となってしまい、部品が大量に余る/営業の増産要求に対して対応する生産設備の能力が不足して期日までの増産対応が出来ずに欠品、といったことです。
これらは、オペレーションレベルで業務改善やシステム導入をしてもマネジメントレベルの改善を図らない限り、効果が限定的になってしまうことを示しています。うまく在庫が適正化出来ている企業は、マネジメントレベルの改善、つまり上位の計画精度が高く、意思決定のルールが明確になっています。そこで、大きな目線で在庫適正化を図るためのマネジメントレベルの一般的な問題点を列挙してみます。
①基準が存在しない
まず一般的な流れとして、経営計画→販売計画→生産計画→購買計画といった風に計画が繋がっていきその後企業活動が実行されます。この計画の時点で、例えば営業と生産で需給調整が行われます。この需給調整をする際に、営業部門の販売計画、製造部門の製造能力、購買部門の調達制約などを考慮しないといけません。制約が全くない場合であればよいのですが、残念ながら企業のリソースは限られているため、優先順位や諦めたりする要素を決めていかねばなりません。これらの制約を考慮するための基準が整備されていないことが多いです。例えば、全ての顧客に製造できない場合、どの顧客を優先するかの顧客優先度。どれぐらいの納期で納めるかの標準的な納期の基準。設備の稼働と製造数量の能力制約。製造の計画変更が許されない変更不可期間の設定。在庫の責任部署や基準在庫のルール。どういう状態になれば終売とするかの終売ルール。これらが曖昧、もしくは整備されていない場合は、サプライチェーンの改善、及び在庫を適正化するための判断の拠り所がなく成り行きとなってしまいます。結果として在庫が減らない状況となります。
②販売計画の精度が低い
①でも見たように、上位の経営計画や販売計画がその後の工程の生産や購買計画を規定します。そのため、できるだけ精度高く経営計画や販売計画を立てる、ことこそが在庫の適正化に繋がります。尚、精度が高い、というのは売上数量を単純に高めに設定すればよいとか、前年より今年を低めにしておけば数量は製造や物流の許容範囲内に収まるはずだという希望的なものではありません。そして個々の部門がそれぞれの思惑で勝手に作るものでもありません。特に開発、営業、製造、物流といった部門が合意して策定することが重要です。営業はいかに目標数量を売り切るか、製造はいかに品質を保って定められたコストを達成するか、開発は売上を上乗せする魅力的な製品をいかに開発できるか。こうした思惑を組合わせて目標数量を作り切り、売り切る覚悟を持って経営や販売計画の精度を現実的に妥当なものとします。
この2つを留意することで、現場のオペレーションだけでは達成できない在庫適正化を大きく前に進めることができるはずです。