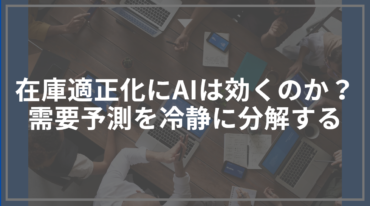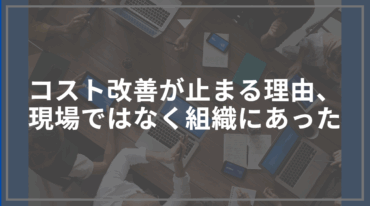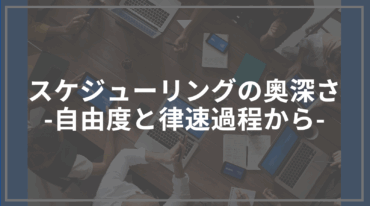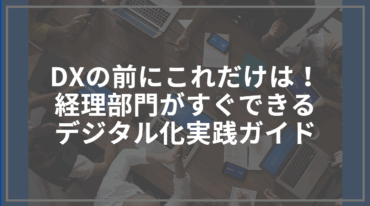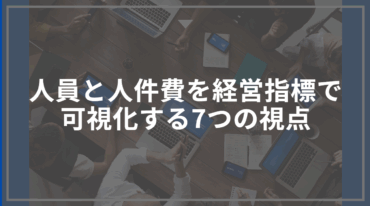企業活動の目的というと、狭義には利益の最大化、と言えるかもしれません。ビジョンの達成という大目的と併せて利益を上げることは大切です。しかし、利益の追求をすることが、企業の繁栄や継続に資するのか?という疑問もあります。SDGsやESGといった商売とは異なった文脈ではなく、売上や利益をどう上げていくことが最も企業の存続に活きるのか、それが在庫の適正化とどう繋がるかを語ります。
在庫は企業の中では資産の扱いです。特に製造業や卸売小売業では貸借対照表上で大きな比率を占める項目ですし、それ以外の建設業や運輸業でも在庫は重要な位置づけです。また、サービス業であっても、ヒトがどう稼働しているか、というのは重要な視点です。昨今、上場企業でも資産の効率性を上げるのが重要な観点だと言われています。そこでまず資産の効率性を示す指標を整理します。
■資産効率性の3指標(ROA ROIC ROE)
売上高営業利益率、といった売上や利益に関する損益計算書の指標はピンとくる方が多いと思います。しかし、資産効率と言われると考え方がやや理解やイメージが難しくなってくるのではないでしょうか。ざっくりいうと資産効率性とは、事業を営むことでお金をどの程度効率よく回し、利益を生み出したかを表す指標となります。
①ROA アールオーエー Return On Aseet 計算式:営業利益÷総資産 (※厳密には営業利益ではなくEBIT)
自社の貸借対照表の左側に表記されている全ての資産を使ってどれだけ利益を上げたか、を示す指標です。最も簡単に資産効率を表せる指標ですが、事業に直接用いていない資産を多く保持している場合は数値が低く出てしまいます。各種資料を参考にすると、上場企業でのROA平均は3-4%程度です。
②ROIC ロイック Return On Invested Capital 計算式:事業利益÷投下資本 (※厳密には事業利益はNOPAT)
自社の資産から、事業に用いている資産のみを抽出して、それに対してどれだけ利益が生まれたか、を示す指標です。ROAの分母の総資産から余剰資産や買掛金などの運転負債を取り除きます。事業そのもののの稼ぐ力を直接表す指標なので、企業の実力を測れます。(財務レバレッジによる影響も除外できる)各種資料を参考にすると、上場企業でのROIC平均は5-6&程度です。
③ROE アールオーイー Return On Equity 計算式:当期純利益÷純資産
株主から拠出された投下資本に対して、どれだけ利益を生み出したか、を示す指標です。どの程度の利回りを株主に対して生んでいるのかが理解できるものです。ただし財務レバレッジをかけることで人為的に高めることができてしまいます。上場企業では開示を義務付けられており、異業種間の比較もしやすいです。各種資料を参考にすると、上場企業でのROE平均は8-10%程度です。
■経営のタイプ
資産効率と繋がる話として、経営のタイプを整理していきます。経営のタイプとは、どういう風に売上や利益を上げていくかの大枠の考え方を指します。
①額を大きくする
最も一般的な経営の考え方として、額の経営です。売上高や利益の「額」を大きくし、それを成長させることを重要視します。売上さえ大きくなれば少々費用がかかろうとも利益も並行して伸びる、です。人口が増加し、単一の需要群がある中で、経済の規模もそれに伴って大きくなる時代では合理的な考え方でした。
②率を大きくする
次に、率の経営です。売上高や規模も大事ですが、そこからどれだけ効率よく利益やキャッシュを生み出しているかを重視します。絶対額ではなく、比率を見ます。経済が成熟して求められるものが多様になる中で、規模の拡大ではなく効率を追求することは理にかなっていると言えます。
③利回りを大きくする
最後に、利回りの経営です。売上高と利益の効率性を見るのではなく、投下資本という元手に対して、どれだけ効率よく利益やキャッシュを生み出しているかを重視します。経営に投資の考え方を導入したものです。①と②は損益計算書の枠内での発想でしたが、③は貸借対照表も含めたBS思考になります。
この3つの経営のタイプのうち、上場企業の業績や株価を最も長期的に上げたのは、③の利回り経営です。額や率の経営も勿論大切です。ただし、額や率の経営は、短期的な施策や目標に縛られがちな単利思考になります。利回りの経営は、投下した資本から上がった利益でまた投下して、、という複利での長期的な考え方になります。2,3年の短期的な業績向上を狙うのであれば率や額の経営でもよいですが、企業は基本的にそれ以上の継続性を持つ存在。そうなると利回り経営が最善ということになります。
■在庫の適正化とROIC+利回りの経営
ここまでを整理すると、経営のタイプとしては、利回りの経営が望ましい。利回りの経営の良し悪しを測るには資産効率の指標がよい。その中でも事業そのものの稼ぐ力を示すROICが最も望ましい、となります。このROICで用いる事業用資産は、「在庫」を含めています。在庫、つまり棚卸資産は、各種資料での上場企業での占める比率の平均は12%程度です。他に大きな比率のものは設備や売掛金などがありますが、12%は大きな数字です。設備や売掛金と異なり、在庫は比較的増減を自社で管理可能なファクターとなります。この投下資本=在庫をいかに効率よく用いていくか、というのは利回りの経営に重要な要素となってきます。
在庫を具体的にどう適正化するか?という手法論の話ではなく、目線を経営レベルに上げてみました。経営のタイプ、資産効率性の話から在庫へと至る位置づけ。まずこのように大上段から在庫を捉えてみるのもいいかもしれません。