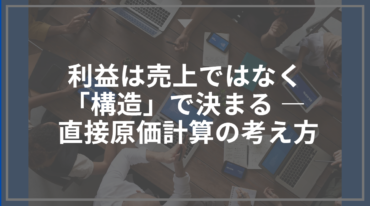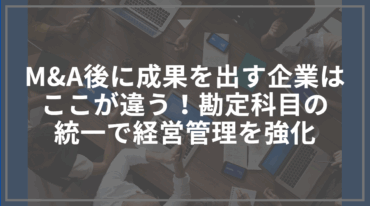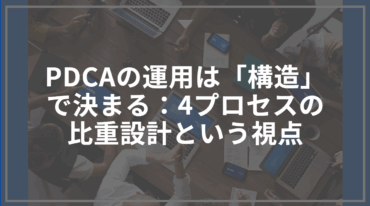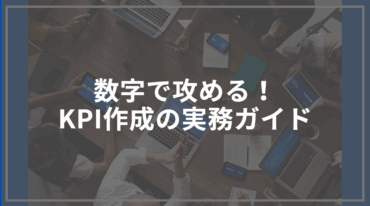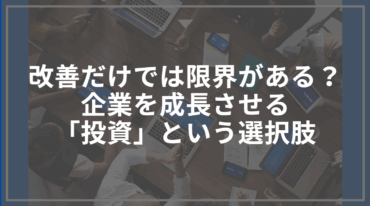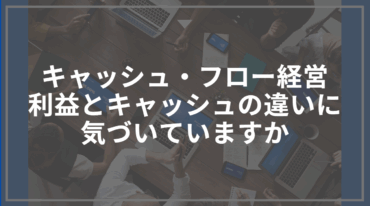今回は、原価計算で採用する手法のうち、「標準原価計算」を扱っていきたいと思います。それぞれ定義、目的、採用率、現在の状況にそって紹介していきます。
定義
まずは念のため定義から。標準原価計算は、製造業などで使われる管理会計の手法の一つで、あらかじめ定めた「標準原価(あるべき姿の原価)」と、実際に要した「実際原価」とを比較して差異を分析する仕組みです。材料費・労務費・経費について、技術的・経済的に妥当だと考えられる「予定の原価」をあらかじめ設定しておき、標準と実際の差額(差異)を分析し、なぜズレが生じたのかを把握します。
目的
次に、標準原価計算の目的を見ていきます。主に5つほどあります。
①原価維持/統制に資するため
②原価改善/低減に資するため
③予算編成と統制の基礎資料とするため
④棚卸資産/売上原価の算定基礎とするため
⑤決算早期化のため
このうち、主たる目的として比率が高い順に、
②原価改善/低減に資するため
④棚卸資産/売上原価の算定基礎とするため
③予算編成と統制の基礎資料とするため
と続きます。②が最も大きいのは、標準原価計算の定義にもあるように、標準と実際の差異を分析してズレを発見し、改善していくところが本流だからであると考えられます。
採用率
標準原価計算という手法は、原価管理で必ず採用しなくてはならないものではなく、選択制です。そのため採用しない企業もあります。そこで標準原価計算を採用している比率を見ていきましょう。製造業と非製造業とで大きく分けて標準原価計算の採用率を分析してみたところ、1990年代以降で変化しておらず、製造業が50%程度、非製造業で22%程度です。(日本大学商学部会計研究所の調査を参考)この理由としては、まず製造業はモノを作るため、原価管理が中心課題になりやすいということです。製品1単位当たりのコストを把握して儲かっているか否か、過剰な費用を要していないかなどを検証します。一方で、非製造業はサービス業的な面が強く、標準原価の設定が困難です。どちらかというとモノではなく人件費や時間の配分が主で、製造業のような繰り返し作業や材料の投入が少ないという背景があります。
製造業でも採用率が50%程度と低く見える理由は、製造形態の多様化が影響していると思われます。同じものを大量に作る量産型だと標準原価計算は極めて有効に働きますが、多品種少量や受注生産型だと標準を設定する手間が大きく、他の管理手法で済ませることが多いからと思われます。更に、システムや運用面的な問題として、標準の設定や差異分析の仕組の負担が重かったり、そもそも生産管理システムで実際原価を素早く把握できることで、標準原価にこだわらなくてもよい、という企業が増えているからです。
現在の状況
採用率のところでも触れましたが、標準原価計算はやや陳腐化してきているのが現状です。理由として、
①機械/自動化によって設備導入段階でほとんどの原価が確定してしまい、原価改善の余地が少ない
②市場の影響で売価の下落が標準原価より大きく、標準原価が基準として機能しない
③原価標準の設定の際に、恣意性の余地があり、容易に標準原価が達成されてしまう
④製品lifecycleの短命化、生産方式の短期間での変化により基準としての標準原価設定が困難に
これら4つの要因により、標準原価計算の役割が低下している傾向が読み取れます。ただしERPパッケージソフトウェアでは標準原価計算が基本機能として搭載されているので、ERP自体がより浸透すれば標準原価計算の採用割合が増える可能性もあります。一昔前では有用であった標準原価計算。今でも勿論有用ではありますが、市場の変化が速く、製品が多様化進み、かつサービス業化が進むにつれて、少しづつプレゼンスが下がっているのかもしれません。