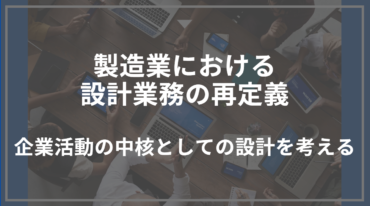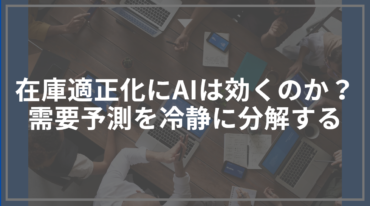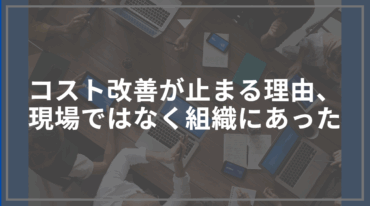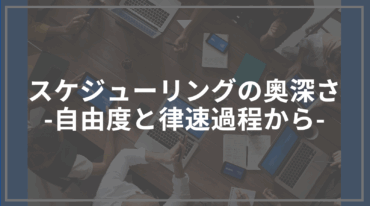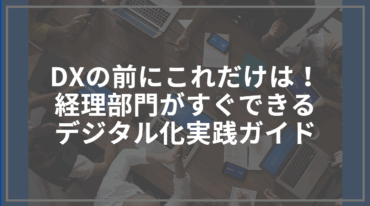最近は、ジョブ型人事や人的資本経営などが注目されています。人手不足が叫ばれている中で、いかに優秀な人材を確保して魅力的な役割を設計し、企業の発展に貢献してもらうかが議論されています。報酬と役割の設計、業務の可視化、キャリア形成支援などは書籍や知見が多くなってきました。
しかし、企業として、人を雇って業務を遂行してもらうという投入量と、それに見合った成果としての産出量をマネジメントする視点が薄いように思います。どうしても人員を雇う=人件費、と費用とする扱いが合理的すぎて人間味に欠けることがこの議論を避けてしまっている要因かもしれません。とはいえ、企業体として事業を存続・発展し続けるためには避けて通れない話題ではあります。そこを今回は人材を投資として管理する視点を、具体的な数値指標から解説していきます。
特に、今回のテーマは人事の話というよりも、業務効率化/生産性向上/人員配置などの前提として話していきたいと思います。例えば業務効率化の話でよく出てくる話題は、とにかく10%生産性を上げよう、身の回りの困っている業務の生産性を上げよう、出来る限り業務を効率化しましょう、といった話を聞きます。こういったボトムアップ型や成り行きでの業務改善はあまり効果的に進むことがありません。財務諸表の損益の観点からできるだけトップダウンかつ全体俯瞰で進めることが肝要です。業務効率化などの活動が短期的だったり局所的にならないようにします。業務効率化などのテーマは細かい現場の業務や事情をつまびらかにしないと進まない局面もあるため、全てをトップダウンで進めることはできません。その辺りはバランスが必要になってきますが、まずは大きな絵を描くところが重要になってきます。
さて、人員と人件費のマネジメントを扱っていくわけですが、まず第一歩として現状の可視化をお勧めします。過去と現在の整理です。将来の推移や計画となると次のステップになるので、まずは現状把握から。意外に現在どのようになっているかはわからなかったりします。まずは人員と人件費の関わりがわかる指標をつまびらかにすることで現状を把握しましょう。7つの指標を挙げてみました。7つ以外にも離職率や残業時間など人員と人件費に関わるものはありますが、捉えられていることが比較的少ないが重要であるものに絞ってみました。(平均値に関してはざっくりしたものであるため参考程度に)
①売上高人件費比率
定義:人件費÷売上高×100%
意味合い:最も基本的で重要。人件費が売上に占める負担感を示す
平均値:製造業10-20%、サービス業30-50%
②平均年齢/年代別人員数
定義:従業員の年齢の単純平均
意味合い:年齢や等級による人件費の増減、退職数の予測を示す
平均値:全産業平均43歳(厚労省調査)
③属性別比率
定義:従業員及び工数のうち、正社員、アルバイト、派遣、外注の比率
意味合い:人件費が変動的か固定的か、柔軟性を示す
平均値:サービス・小売 非正規率50%以上、製造業 非正規率20-30%
④管理職比率
定義:管理職相当以上の人数÷全社員×100%
意味合い:管理が強めなのか管理が行き届いていないなのかといった管理力を示す
平均値:中堅大企業10-15%
⑤間接機能1人あたりカバー人数
定義:間接人員1人あたりが支える社員人数
意味合い:間接機能の弱まりや肥大化をしていないかを示す
平均値:大企業100-200人、中小30-80人
⑥人件費効率
定義:売上高/利益÷人件費
意味合い:人件費をうまく活用出来ているかを示す
平均値:およそ5-10倍
⑦工数コスト効率
定義:売上高/利益÷工数コスト(人件費+外注費)
意味合い:外注費も含めた工数全体の活用が出来ているかを示す
平均値:およそ2.5-5倍
まずはこれら7つの指標を可視化することによって現状が把握できると思います。特におすすめなのは、人件費効率もしくは工数コスト効率です。これは人員の投入が売上や利益にどう繋がっているかを示す「投資」的な指標です。人件費という名称から単純にお金が出ていく避けられないもの、という認識では今の時代の競争を勝ち残ることは難しいと感じます。これら7つの指標は、過去からの推移を並べてみたり、組織別や拠点別に切り口を変えてみると更に現状が浮き彫りになってくるでしょう。次回は、これらの指標を踏まえながら、今後の改善の方向性を探っていくところを扱っていきます。