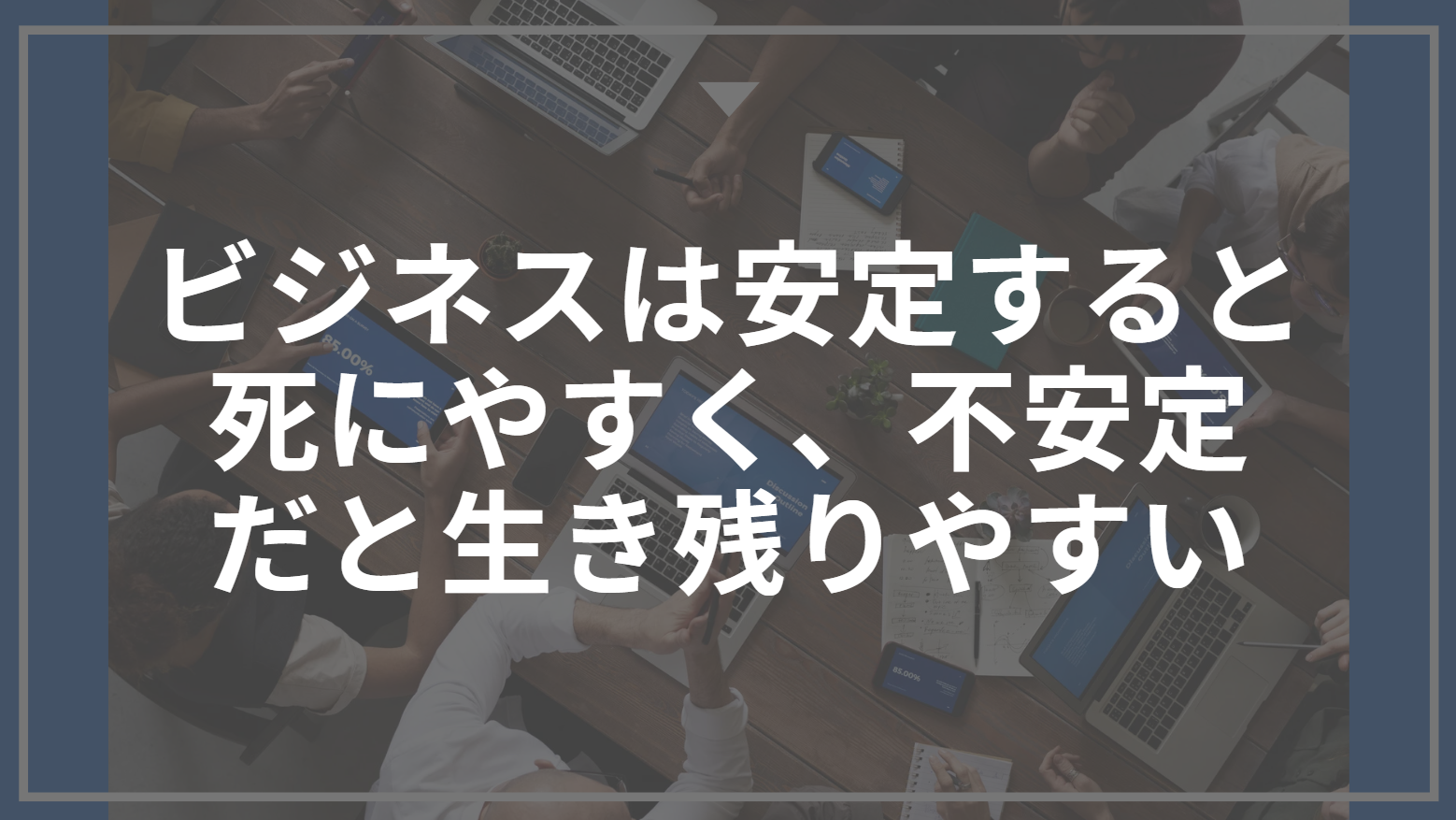今回は、個別の企業に焦点を当てて扱っていきたいと思います。個別の企業の取組みから、弊社のテーマである企業変革に繋げる示唆を得ようという目論見です。
ドン・キホーテ。ドンドンドン・ドンキ、ホーテー、という店舗内のサウンドが耳から離れない総合小売店のドン・キホーテを取り使います。狭い通路に山積みにされた圧縮陳列と独特なPOP。かつてはヤンキーのたまり場とも揶揄されており、不祥事を起こしたため治安の悪化を招くなどして出店反対運動などが起こったこともあります。異色の小売店ですが、ドンキを運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)は2019年総合スーパー大手のユニーを完全子会社化して2024年には売上高2兆円を超す総合小売グループとなりました。時価総額は2024年3月で2兆6000億円。なんと日本の小売業界の売上高4位。セブン&アイホールディングス、イオン、ファーストリテイリングに続く4位。正直ここまで大きい企業と思わなかった人が大半なのではないでしょうか。老若男女が足を運び、10代20代半ばのZ世代の間で絶大な支持を得ている。円安を背景に急増しているインバウンドも良好。そんなドン・キホーテは他と何が違うのか。その特徴を取り上げてみたいと思います。非常にユニークな取り組みが数多ありますが、本質的な1つに絞ってみたいと思います。
それは、「主権在現」です。
現場に徹底して権限を委譲するドンキの鉄則を示します。現場から離れた本部よりも、消費者と日々接している店の方が圧倒的に顧客理解は高いはず。そうであれば、思い切って現場を信じて現場のあらゆる権限を渡してしまおうという発想です。この発想はセオリーと真逆です。なぜなら、日本の小売業界は、米国生まれの「チェーンストア理論」を手本としてきたからです。これは本部にあらゆる権限を集中させ、店舗は販売に専念させることで経営効率を高める思想です。どの店も同じ商品やサービスを扱い、同じ棚割りとなる。店舗の設計を標準化することで品質を担保しながら効率的に多店舗展開へ繋げられます。ドン・キホーテを創業した安田氏は、小さな会社で大資本の店舗思想と同じやり方をやっていては勝てないという認識があり、チェーンストア理論を捨て主権在現という真逆をいきました。東京府中市にドンキ1号店を立ち上げたのが1989年平成元年で、当時はバブル経済期。バブルがはじける手前でどちらかというと大量少品種で標準的で効率的なオペレーションを整えれば売れると思われていた時代です。その頃に個性重視の店づくりに舵をきった手腕に敬服します。
具体的には、担当の売り場を決めて仕入、陳列、値付け、ポップの作成、店の演出全般まで全て好きにできます。担当者全員に専用の預金通帳も持たせているとのこと。これを行うことで、社員が活き活きと仕事をしだすようになりました。やはり本部から売る商品、販促、価格、陳列の仕方を全て決められてしまったら工夫をする余地が無く、仕事がつまらなくなってしまうと思います。失敗が起こったり効率性は低くなりますが、その分モチベーションが上がります。現場の担当者が狭くて深い権限を行使し、売れたかどうかの責任まで負う、だからこそ時流に合った、常に鮮度が高い店が出来上がります。また、承認欲求を満たす、といういい方もできるかもしれません。ドン・キホーテは圧倒的に多数は地方郊外のお店であり、現場で働く人の親類や知人が訪問してきたときに、自分が作った商品や陳列を見てもらって面白い/買いたい、となれば承認欲求が満たされ、より工夫に邁進する、ということです。組織の強さというよりも個の強さがあるのがドン・キホーテと言えるかもしれません。
主権在現と連動する考え方として「顧客親和性」もあります。これは、店づくりには想定顧客に最も近い店員が関わるべきという考え方。名古屋駅前のファッションビル近鉄パッセにあるキラキラドンキ(2024年4月)でも、平均年齢19歳というZ世代ど真ん中のスタッフが集まったと言われます。キラキラドンキとは、特化型店舗で、10代から20代半ばのZ世代をターゲットにした店舗で、コスメやスキンケア、ヘアケア、カラーコンタクトなどかわいい/きれいの商品を押し出した特徴を持ちます。店員がZ世代だからこそ、Z世代のトレンドがわかり、周りで流行っているアイテムを積極的に仕入れ、SNSを駆使してインフルエンサーたちの愛用品を確認します。その中から新たな売れ筋が見えてくることに繋がります。これは主権在現だからこそできる人材登用の考え方で、本部主導での画一的な採用であれば成し得なかったことだと思います。
ここまでの話を一般的な話へと昇華すると、企業の業績向上には活力ある人の存在が必要だと言えると思います。これはなんら新規性の無い話に聞こえます。しかしながら単純に、福利厚生の充実やキャリアパスの明示、魅力的な仕事の提示をするということに留まらず、ドン・キホーテの場合はメンバーが自律的に工夫する仕掛け(=主権在現)を最大限取り入れていることが異なると思います。裁量が広ければ広いほど人は面白いくらい勝手に熟達して工夫するようになる、仕事に満足するようになるということが言えると思います。逆に、統一的な手順、ルール、方針がガチガチに存在すると、例え待遇が良かったとしても工夫しようとか仕事に満足だ、自分の人生を生きている、とは思わなくなると感じます。その代わり、標準化による効率性を犠牲にするという多大なるデメリットを超える力を認識しなければとても導入できません。しかし売上2兆円をこえる企業に成長していることからも主権在現は企業の業績向上に役立つ考えだと証明されていると言えると思います。
自社のメンバーを信じて思い切って任せてみる、そういう企業の舵取りもよいのではないでしょうか。
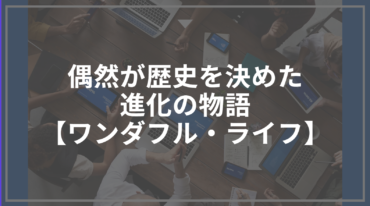

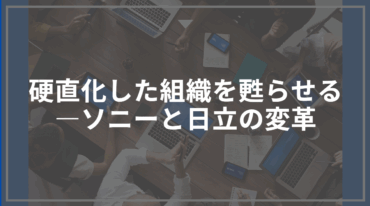
.png)
.png)