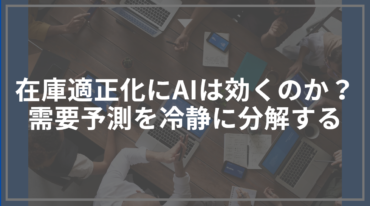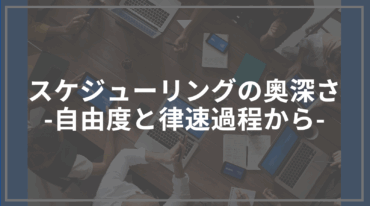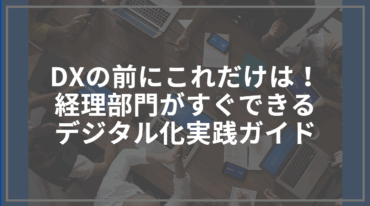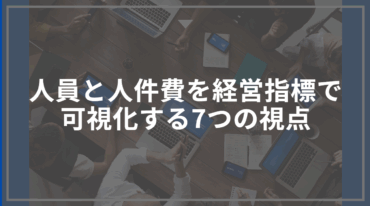前回は「コスト改善はまず間接材から」の流れの中で、その取組みが進まない背景にある“土台”――「一元管理」の不備について触れました。しかし、土台が整ってもなお、改善が進まないケースがあります。今回はその理由を、組織の仕組みと文化の観点から見ていきましょう。
コスト改善が止まる理由➀ 現場担当者の動機付けが不足している
コスト改善が進まない理由として最も大きなものは、「現場担当者の動機付けが不足している」です。言い換えると、コスト改善に頑張って取組むメリットがない、ということです。殆どの日本企業の調達に関わる組織(総務、管理、購買など)にとって、コスト改善で成果を出したからといって、その担当者が直接的な報酬を得られる仕組みにはなっていません。それどころか、年功序列的な評価が続いていたり、成果を出したかどうかよりも調達におけるトラブルやミスが起きていないことが評価されたりします。
積極的にコスト見直しに取組んだ場合、値下げ交渉に留まらず、現場の業務変更が付随して起こります。例えば既存の取引先を別企業に変更した場合、自社の設計や製造、及び現場の担当者と調整が発生し、工数負担が増します。そして調達する品目やサービスが変更になれば、品質のブレや受入れ/検収など何らかのトラブルが起こる可能性も増します。ここまで踏まえると、評価もされないし、工数負担も増えるので、何も変えないのがベスト、と現場担当者が思ってしまうのも無理はありません。また、コスト見直しに前向きであったとしても、通常業務で忙しい中で日常業務の範囲内で取組むべきものと上から認識されており、時間が割けないので取組みがいつの間にか立ち消えしているケースもあります。
コスト改善が止まる理由② 見直しが難しい領域がある
次の要因は、「見直しが難しい領域がある」です。社内で聖域扱いされており、見直しの対象外となっている領域がある場合です。なぜそんな領域ができるのか、というと、長年同一の担当者で固定されており、第3者から実態がわからないことがあったり、同じ取引先と長年取引を行っているため、馴れ合いで継続が前提になってしまっているケースがあるからです。また、創業者と懇意にしている昔からの取引先のためスイッチすることが難しいことがあったりします。これは特にガバナンスが効いていない中小企業で、人員交代の余裕が無かったり、関係者や外部専門家からの指摘が無かったりすることによって起こり得るものです。
コスト改善が止まる理由③ 専門性の不足
これまで見てきた2つの要因に比べて重要性は下がりますが、「専門性の不足」も挙げられます。現場の担当者が不足に感じて歯がゆい思いをしているというよりかは、「毎年しっかり見直しは行っている」、「現状が最安値の水準のためこれ以上は難しい」、と担当者が考えているため、本当はどれぐらいの改善余地があるのかが上位者や経営陣から判然としないことがあります。ふたつめの要因で挙げた長年の取引で馴れ合いとなっているところからも、新しい先を含めて比較検討したり、費用が変わる要素を見比べてみたりといったことをしないために、知見が溜まっていかないのもあります。またそれを助長するように社内で単価や条件、交渉内容などを蓄積して共有する仕組みやツールが不足していることも挙げられます。
コスト改善が止まる理由④ 役割の曖昧さ
最後に、「役割の曖昧さ」が挙げられます。これは企業や組織全体で、調達コストを〇〇%削減といった目標は掲げられるも、目標の根拠であったり実際にどんなアプローチで誰が何を担当して、といったところが不明瞭で、あとは現場担当者任せ、になっている例です。総務部や管理部、調達部と外部に委託発注したりモノを購入したりする部署が社内で分散しており、全社的な方針や重複を避けて物量を纏めて発注するなどの施策が打てていないケースもあります。
コスト改善が進まない理由は、コスト見直しの専門知識が直接的に不足していることよりも、「現場担当者の動機付けが不足している」「見直しが難しい領域がある」「役割の曖昧さ」といった組織の仕掛けや文化が大きな影響を与えていることがわかりました。これらは、少数の現場担当者が奮闘するだけでは解決できません。コスト改善は現場努力の問題ではなく、組織の仕組と文化の問題です。目の前のコストを削る前に、まずは“仕組みと文化”を整えること――そこからが本当の改善の始まりです。