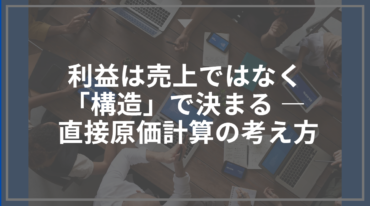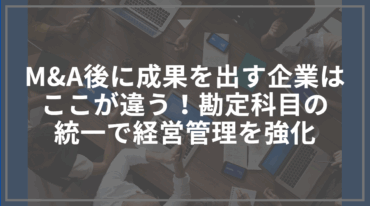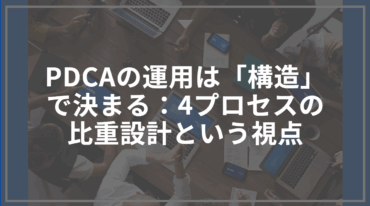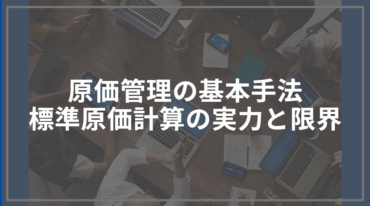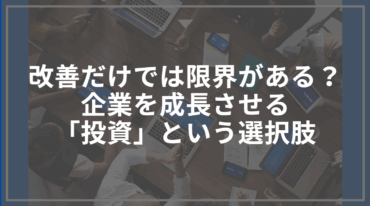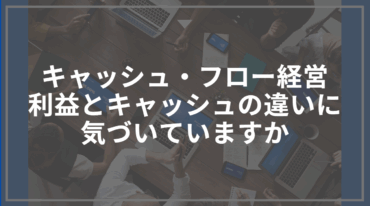KPIを設定するのは重要だ、という認識はあるものの、ではどうやって設定すればよいのかわからないことが多いです。とりあえず計測できるものをKPIに設定するのは上手いやり方ではありません。そこで、今回はどうやってKPIを作っていけばよいのかをステップで解説していきます。
①ゴールの設定(=最終的なKPI)
②差異の確認
③プロセスの確認
④肝の抉り出し
⑤目標設定
重要となる5ステップをまずは解説していきます。(KGIやKPIと分けるとややこしいので今回はKPIに統一します。)
①ゴールの設定
まずは最後に目指すべき到達点を設定します。企業の到達点としてビジョン、例えば検索のない世界を作る、とか全ての人に綺麗な水を、などがあると思います。これも確かに到達点ですが、その到達点を具体的に数値に落とし込んだもの=KPIを設定します。企業体として最後の成績となるのは財務諸表上の数値なので、売上や利益が基本的には到達点の数値の設定になります。まずはこれを設定しましょう。ちなみに先ほどのビジョンを財務ではなく数値に置き換えて目標とするならば、google検索数がどれだけ減少したか、とか井戸水を飲んでいない人の数、などが設定されるでしょう。但しこれは企業体の最終成績ではありません。そして、その目標数値をどう設計するかも大きな論点としてあると思いますが、今回はKPIの作り方なので、目標設計は別途扱います。ここでは目標設定はできたものとして進みます。
②差異の確認
次に差異の確認です。差異というからにはふたつの数字が登場します。売上や利益の目標と現在です。目標は①で設定し、現在は計測済みであるという前提です。そして目標を達成するときには期限があります。その起源に到来したときに、成り行きで過ごした場合の現状がどうなるかを予測します。その差異を確認するというステップです。成り行きというのは特段の努力をせずに、現状のまま推移したらどうなるか、ということを指します。通常であれば、目標と成り行きには差が出るはずです。差が出ない場合は目標が低すぎるか、成り行きで予測するのが楽観的、もしくは現状物凄い努力をして成り行きですらとてつもない労力が反映されている、といった状況かと思います。この場合、新たなことは何もする必要がありませんが、ここでは差が出るという前提で次のステップにいきます。
③モデル化
このままでは目標が達成できない場合、どうするのでしょうか。基本的に通常のビジネスは、売上-費用=利益です。非常にざっくりいうと、売上を上げるか、費用を減らすかの2択になります。売上をあげよう!や費用を減らそう!では何も言っていないし何の活動に注力すべきかわかりませんので、自社のビジネスモデルがどのようにモデル化できるかを数式で表現してみましょう。単純な式で説明します。売上を上げる場合にどうするか?です。売上を分解すると、販売数量×平均単価と表現できます。ここまでだとまだ粗いです。BtoBの営業だと仮定頂くと、販売数量は訪問数×提案率×成約率と分解します。平均単価は、正規単価×割引率と分解するとします。そうすると、
売上=(訪問数×提案率×成約率)×(正規単価×割引率)
になります。ここで売上を上げる選択肢としては論理的には複数考えられます。訪問数を上げる、提案率を上げる、成約率を上げる、単価を引き上げる、割引をしない、となります。訪問数を上げるには、管理資料を減らすとか会議を効率的にこなす、とか営業ルートを効率的に、などが挙がります。提案率を上げるには、打合せ中は顧客の意見を聞く側に基本的に回るとか、次回までの設計をきちんと伝えるなどが挙がります。他の項目もこうした施策が考えられます。ここまできたらモデル化が出来たといってもよいでしょう。
④肝の抉り出し
③のモデル化まで出来たらあとはそれらを網羅的にKPI設定して素早く実行すればよいのでは?と思われたかもしれません。これだとモグラ叩きに終わってしまいます。肝を抉り出してそこに一点集中する必要があります。今回のステップの中で最も重要かもしれません。描き出したモデル化のうち、まず定数と変数を分けます。定数は基本的に動かすことができない、もしくは動かせる範囲が狭い、ものです。今回でいうと、正規単価と割引率、そして訪問数です。正規単価は組織で決まった一律のものがあるため定数です。割引率は一見変数のように見えますが、想定している顧客企業では、価格弾力性が低く(=割引しても受注率が増えない)、定数と置いても差し支えないということがわかりました。訪問数は、営業マンの数を増やせば上がりますが、新たに採用するのは予算から厳しいので定数、とします。そうすると、他の提案率と成約率が変数であると判明しました。
提案率と成約率をつぶさに観察すると、成約率は高いが提案率が低いことがわかりました。提案さえできていれば成約率は高いという状況です。そもそも顧客に提案ができていないことがわかりました。営業が何を提案したらよいかがわからず、既存の馴染みやすいものしかできていなかったのです。そこで、営業マンを教育し、顧客の想定される課題とサービスに習熟してもらい、提案の幅を広げて提案数を増やすことにしました。
⑤目標設定
最初のゴールの設定と何が違うのか、という話から始めますが、ゴールは財務成果の最終結果を指し、この目標設定は、④で抉り出した肝の部分についての具体的な目標設定になります。提案数を増やすことが肝だとわかったところで、目標を設定します。売上目標が100万円だとすると、訪問数1,000件、成約率10%、正規単価10万円、割引率0%と仮定したとします。提案数を逆算で求めると、100万円=1,000×□%×10%×10万円×100%の□の部分を求めることになります。すると、提案率は10%で100件が目標数値になります。なんとなく100件ぐらい提案すればよいのでは?といった感覚的な話から、売上100万円が目標ならば肝となる提案数はどの程度必要なのか、が論理的に説明できるようになりました。
KPI作成の重要な5ステップをご紹介しました。顧客企業をご支援したときの例として、③モデル化を行っていてロジカルに進めていらっしゃるケースもあります。しかし上流の最終成果のゴールとの結びつきや差異が不明で、どこに向かっているかが曖昧となっていることがあります。また、①~③まで適切に取り組むも、④肝の抉り出しが行われておらず、KPIが乱立して現場が疲弊しているというケースもあります。④まで行えれば、⑤は円滑に進むと思いますので、まずは①~④を一通り実行してみましょう。