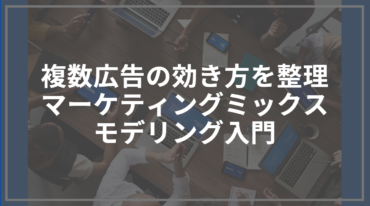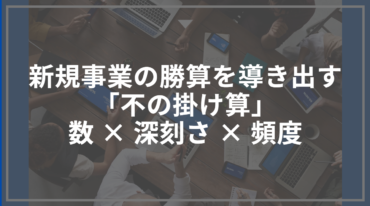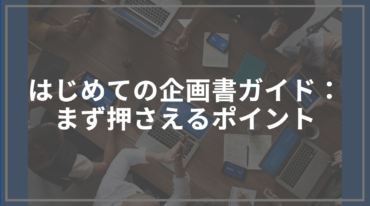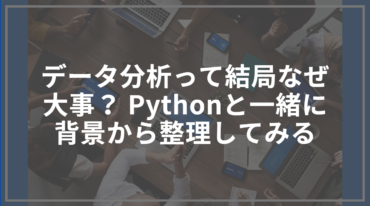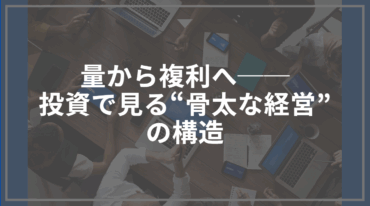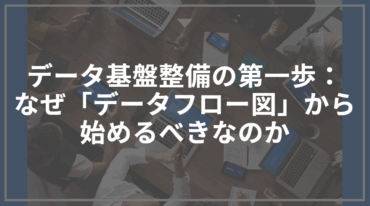今回は、戦略の質を高めることを扱っていきたいと思います。昨今の経済環境を鑑みるに、大胆な戦略を描く必要性は高くなっていると感じています。日本は市場が成熟し、どこの企業も似通ったサービスを提供。生成AIやデジタル技術といったトレンドを捉えた事業モデルが勃興する中で、競争を抜け出すためには競合と異なった大胆な戦略を描いていく必要があります。そうした中で、ではどのように大胆な戦略を描くのか。
まず現状の戦略立案において、大胆さが失われる企業が陥る3つの罠=問題点を見ていきます。
問題点➀ 今までの主力事業にリソースを割いてしまう
歴史がある老舗企業ほど陥り易い罠です。業績が上がっているときはよいのですが、業績が悪くなり、予算を絞るようになると、過去の主力事業に資源を費やしてしまうのです。これは、有望だが不確実な事業に投資するよりも、今までの成功体験にすがった方が良さそうに見えてしまうからです。加えて、現在の経営陣は主力事業の出身であることが多く、ますます既存の有力事業への投資が強固になってしまいます。新規事業への投資がしぼられるばかりか、業績を上げるしわ寄せが既存の有力事業に課されることにもなります。
問題点② 現在の延長線上の戦い方/漸進的な変化の追求をしてしまう
人は失敗を避けるものです。大きな果実が手に入る可能性よりも、小さな損失が気になってします。この心的傾向から、既存の事業をコツコツと改善していく現在の延長線上の戦い方を選んでしまいがちになります。結果、市場シェアを数%引き上げよう/数%の利益をひねり出そう、そのための施策を考えようとなるわけです。大胆な施策は不確実性が高く、自組織のメンバーが実行をイメージしづらい。そういう意味でも漸進的な選択をしてしまうわけです。
問題点➂ 全体的に薄く広く資源を分散させてしまう
ある程度の規模の企業だと事業や部門が複数存在します。各部門の責任者と協議して次年度以降の予算を決めます。責任者は自組織の存在を守るため、その組織が伸び悩んでいる/位置づけが低いとしても予算や資源を死守しようと動きます。自組織が価値がない/成長できないと主張する責任者はいないからです。そうして責任者が資源や予算を奪い合う中、戦略策定時点で明確に良い悪い部門は線引きできないので、それらの前年度の数字を踏襲しながら薄く広く全社的に均等配分する現象が起きてしまいます。新規事業/施策への投資は残った分から気休めに配分を受けるため大胆な戦略に結びつかないことになります。
こうした、社内政治として起こり得るものと人の習性として起こるものを避けて、大胆な戦略を作るにはどうしたらよいのでしょうか。次からは解決策を探っていきます。
それは以下の2つを戦略策定の議論に取り入れることです。
➀確率とデータに裏付けられた外部の視点
②確率を左右する10要因
戦略策定の現場では、確実性への追求が確率の議論よりも重視される傾向にあります。そこで確率の考え方を導入しましょう。例えば、過去10年間で2桁の成長を続けているのは同業界で10%であることがわかったとします。2桁の成長を狙う場合、残り90%の企業と比べて優れている戦略なのか?と自問自答します。また、市場平均を上回る業績を収めた企業は50%だとしたとき、半分の企業を凌駕する戦略となっているかを問うことができます。こうした社内の事業の歴史や力関係で戦略を決めるのではなく、外部のデータと確率の目線を取り入れることでまずは客観性を持つことができます。
これを前提として、確率を左右する10要因を取り入れることが重要です。(マッキンゼー調査から引用)
10要因は、他の企業と比較して優れているかどうかが重要です。(記載している閾値は目安としてお考え下さい)
■企業力 スタート時点で企業が活用できる資源 影響力30%
1)売上規模 売上規模が大きいほど有利
2)債務水準 債務が少ないほど良い
3)過去の研究開発投資 売上高研究開発費が大きいほど良い
■傾向 企業を取り巻く外部環境 影響力25%
1)業界トレンド 平均成長率が高い業界ほど良い(最も重要な要因)
2)地理的トレンド 名目GDP成長率が上位40%の地域
■施策 企業が取る活動そのもの 影響力45%
1)M&A 買収案件が自社の時価総額30%以内で、10年で合計が少なくとも時価総額30%に達する
2)経営資源の活発な見直し 設備投資額を活発に再配分する(50%以上を事業部間で再配分)
3)積極的な設備投資 売上高設備投資比率で業界の上位20%に入る
4)効果的な生産性向上プログラム 改善率が業界の上位30%以上である
5)差別化の促進 粗利益の改善で業界の30%に入る
これら10要因を全てを満たす必要は無いですが、総合力が求められます。この10要因のうちなるべく多くで閾値を超える=大胆な戦略を立案して実行することができれば、業界平均を超える業績向上を達成することができます。これらでまずは自社が立案した戦略が大胆かどうかを判断して3,4つは閾値を超えることができるようにするのが重要です。影響力を見ると、単一では「業界トレンド」が肝要ですが、カテゴリーで見ると「施策」が最も重要です。環境や傾向よりも、自社が選択する企業活動が最も影響が大きいことは管理可能という意味で実践もし易いです。特に業界のトレンドは自社でどうすることもできません。その場合は新規事業で成長率の高い領域に移行するという考え方になります。戦略を策定する際、この10要因で自社の立案した戦略が大胆になっているか、の検証ができます。まずは一旦この10要因で自社の戦略を捉えてみてはいかがでしょうか。
今を取り巻く市場の状況、大胆な戦略を阻む問題点3つ、大胆な戦略に向けた10要因を論じてきました。もし業界でトップ水準を目指すとするならば、勘や経験での戦略の立案、もしくは大胆かどうかを検証しないままの平凡な戦略とならないようにしていきましょう。