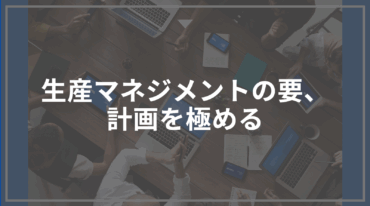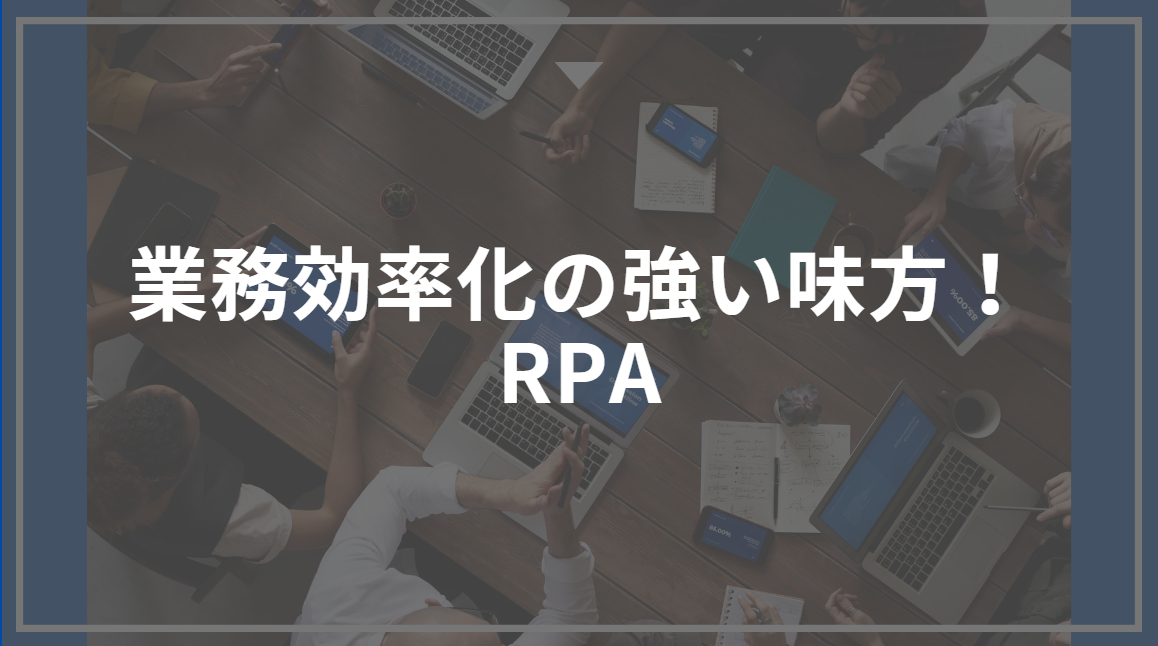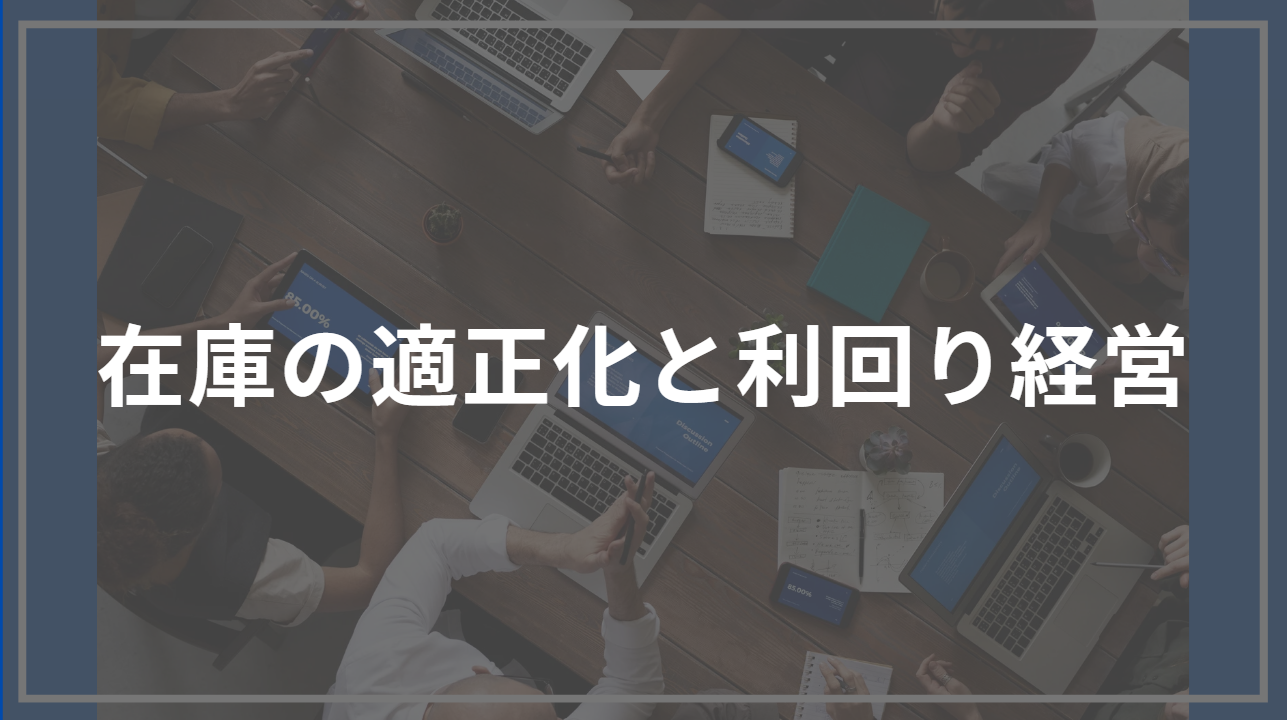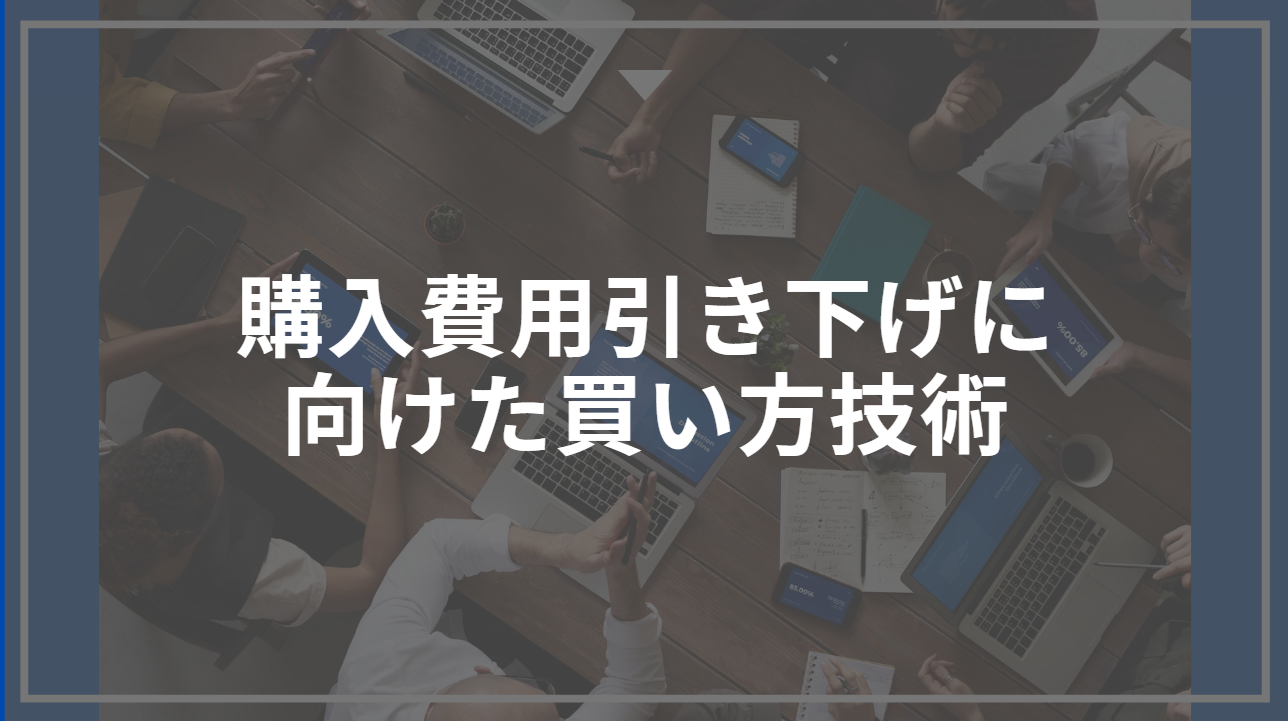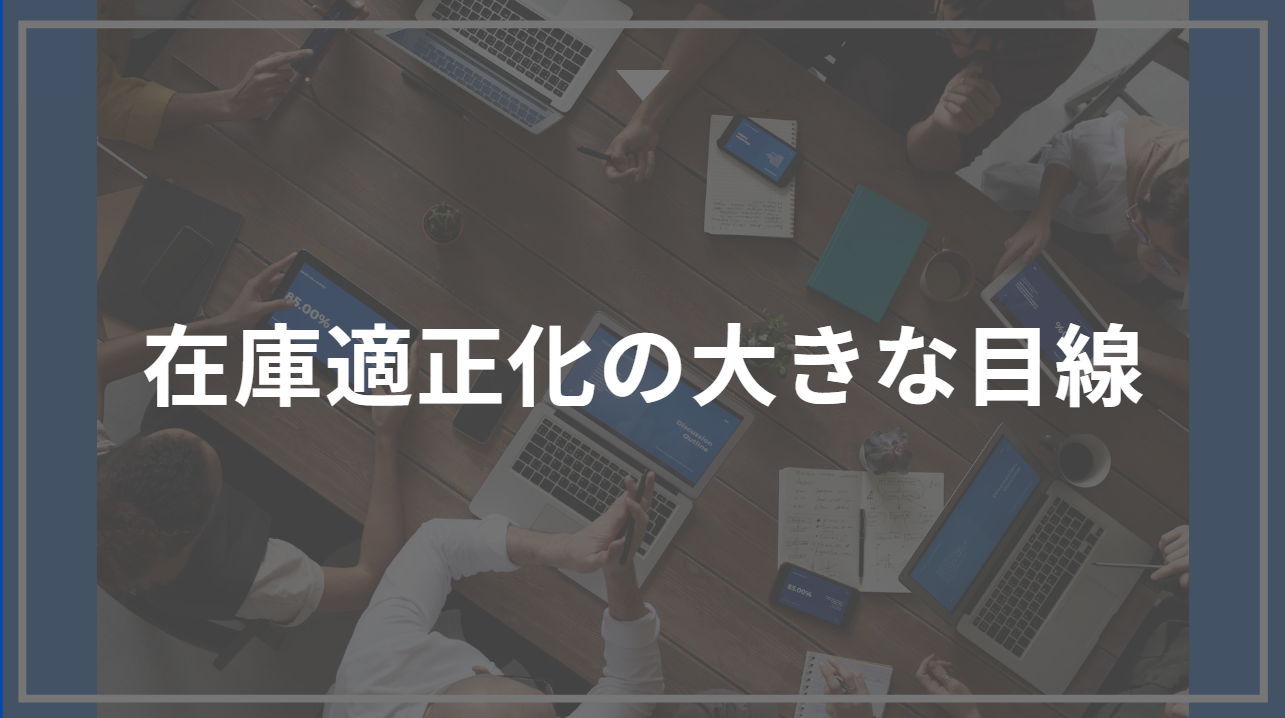今回は製造業の話に入っていきます。弊社は製造業の工場の現場改善と生産管理の改善が得意で支援に入ることがあります。生産管理は製造業で非常に重要な概念であるものの、作ること=製造そのものよりも軽視されがちです。そこで生産管理を扱ってみます。まず生産管理とは何なのか、から始めていきます。
製品の製造プロセスをQCDを満たすように行う管理業務全般
Q=クオリティー 品質
C=コスト 費用
D=デリバリー 期日
具体的な業務とは、5S、作業管理、設備管理、現品管理、品質管理、工程管理、購買管理、物流管理、安全管理、原価管理、計画管理などが挙げられます。produce(=作る)ではなく、management(=管理)の領域を意味していることがわかります。そして生産管理の目的は、売上を増やし、企業の競争力を強化するところにあります。
この定義を見ると、製造業以外にも適用できそうな考えです。汎用的な言い方に直すと、何かサービスや製品を顧客に提供する際に、顧客を満足させる品質で、売値より低い原価で、定められた期日までに納品する、ということです。普遍的に捉えると、生産管理はビジネスマンが普段の仕事でやっていることとほとんど変わらないことがわかります。これはモノ作りではないサービス業やIT、卸売業などでも同じことです。
しかしながら、高度経済成長期の時期とその後の平成/令和の時代では、同じ生産管理でも力点が異なってきています。その点に少し触れたいと思います。
①過去の生産管理
少品種大量生産で作れば売れる時代であったため、如何に人/設備稼働を最大化するか、といった管理の視点でのみ製造を行っていました。生産性さえ上げれば利益が出るのが当然と思われていました。そしてQCD指標だけ管理すれば利益が保証される時代でした。
②現在の生産管理
多品種少量生産で作っても売れない時代の到来です。こうした時代で大量生産を志向してしまうと、顧客の激しい選別、価格の低下、短納期要求といった競争が激しくなる中で売れなくなるので在庫滞留や廃棄、売上減に直面します。QCD管理は勿論のことですが、各種計画(販売/製造/調達/在庫など)の精度を上げることと、需要変動への適切な対応が求めらます。
本来、生産管理という言葉は3つの業務を含んでいます。
①生産マネジメント(計画立案、需要変動対応や調整、リスク対応) 計画こそ王様
②製造・工程管理(製造指示、実績収集、進捗管理 作業統制)
③現場改善(現場の効率性の向上)
本来は3つ全てを兼ね備えていないといけないのですが、過去は②③が主体でも許される時代でした。現在では①②に力点を置かなければ儲かる生産管理としては不十分になっています。
製造業で儲けるために必要な生産管理を扱ってみました。ここまで振返ってみると、前半で記載した生産管理の定義はアップデートする必要がありそうです。